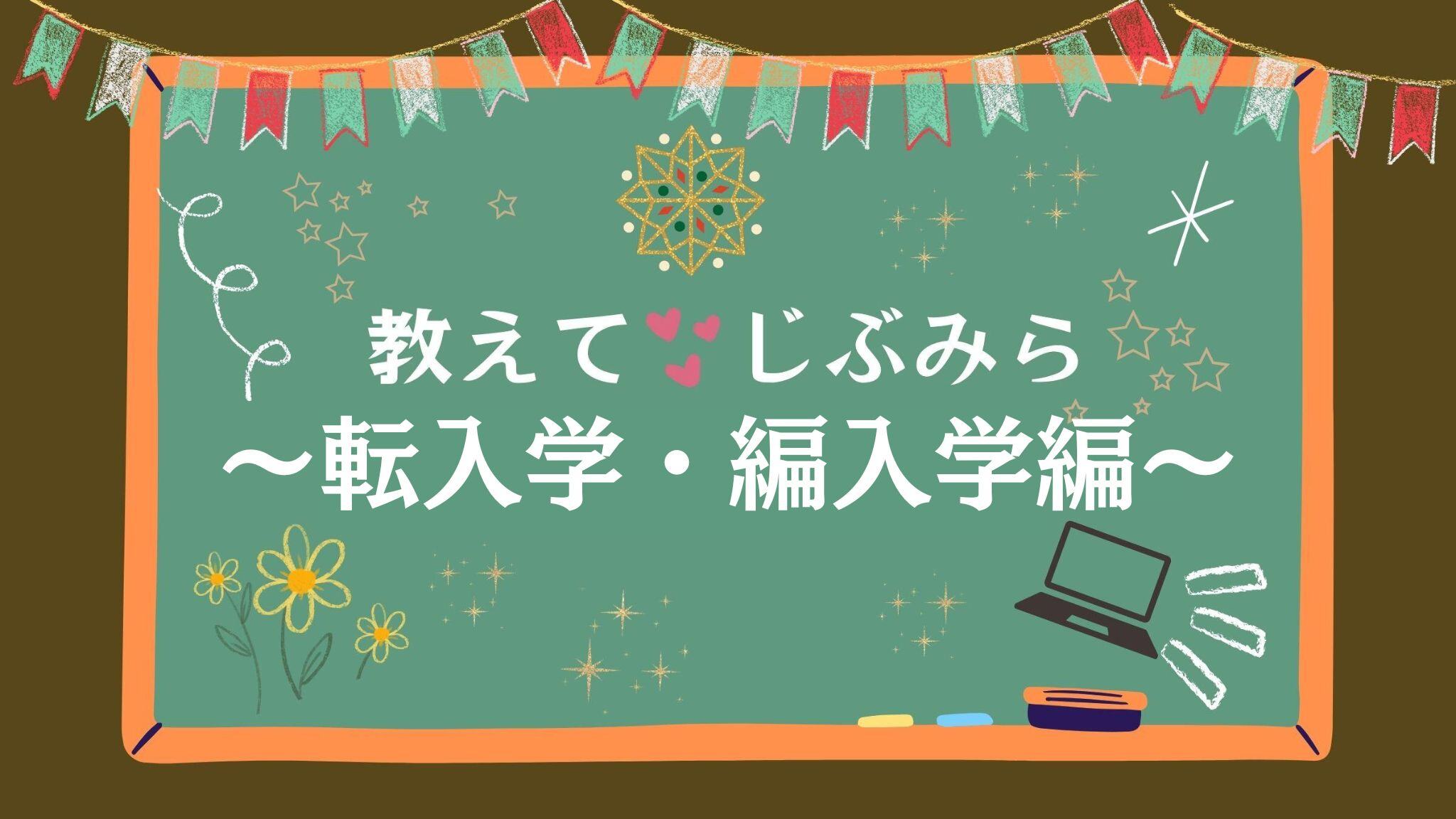食といのちの繋がりを、6教科の視点で再発見!大阪・関西万博からお届けする夏の特別オンライン体験授業Week!🌻

2025年8月5・6・7日の3日間に渡って開催された夏の特別オンライン体験授業。舞台となったのは、大阪・関西万博のパビリオン「EARTH MART」でした。暮らしと学びが融合するじぶんみらい科ならではの視点が交差した授業の様子をご紹介していきます!
視点を変えてEARTH MARTをめぐる、6教科のオンライン体験授業!
「いのち輝く 未来社会のデザイン」をテーマに開催中の大阪・関西万博!
夏休みに入り、現地へ足を運ばれた方も居るのではないでしょうか。

今回、オンライン体験授業の舞台となった「EARTH MART」は、メインテーマを体現する8つのシグネチャーパビリオンのうちのひとつです。

プロデューサーを務めるのは京都芸術大学の副学長であり、放送作家・脚本家として活躍する小山薫堂先生。
小山先生は、テレビ番組『料理の鉄人』や映画『おくりびと』、ご当地キャラ「くまモン」の生みの親としても知られています。
EARTH MARTは、番組制作を通して食を見つめてきた小山先生ならではの、「食を通して、いのちを考える。」展示になっています。
3日間のオンライン体験授業では、伝統や文化、社会課題、現代のテクノロジーなど多角的に食を見つめ直したEARTH MARTをめぐって現地で収録した映像とともに、理科・社会・美術・探究科目・英語・保健体育と、6科目の先生たちが各教科の視点から体験授業を実施しました。
チャットを活用した交流型の授業で、いのちと食の繋がりを自分ごとして考える
各教科の授業テーマをご紹介。
今日から強い魚に改名!!イワシの生態とその歴史(理科)
世界の食卓の裏側、のぞいてみた!?(社会)
見て感じる“いのち”の色(美術)
甘いだけじゃない?未来のお菓子(探究科目)
ITADAKIMASU:More Than Just "Let's Eat"(英語)
「いのちのはかり」で発見!食と自然の不思議なつながり(保健体育)
これらの授業はすべてEARTH MART内の展示から発展させて考えられたもの。
どんな授業なんだろう、と想像力がかき立てられるタイトルです。
例えば、いのちのフロアで特徴的な展示のひとつであるイワシの大群を模したオブジェ。
この展示は、「1匹のイワシが産む10万個の卵のうち、他の魚や鳥に食べられて大きくなるのは100匹程度、さらにその7割は豚や養殖魚の餌になり私たちの食卓に並ぶのは3匹」という想像しづらい循環のスケールを、視覚的に表したものでした。


理科はこの展示を起点に、イワシが生態系全体に大きな影響を与える「キーストーン種」であることに注目。イワシの生態や、私たちの暮らしがイワシにどのような影響を受け/与えてきたのかを考える授業となりました。

参加した皆さんからの感想より。
「命をつなぐ存在としてのイワシに驚いた」
「生態系のつながりがイメージできて面白かった」
社会科のじゅんじゅんも一緒に授業。最後には、日本の伝統的なイワシ料理「鈍刀煮」を食レポ。


探究科目では未来のフロアより、子どもたちの考えた「みんなが幸せになる未来のお菓子」を取り上げ、100年後のお菓子を考えました。好きなお菓子やじぶんが幸せな瞬間を少しずつ掘り下げ、さまざまなアイデアが飛び交いました。


チャットを活用し、みんなの意見や考えが交差する授業は、オンラインならでは。
「仲間と協働して課題に立ち向かい、社会をより良くする方法を探る」探究科目ですが、突然社会全体のことを考えるのではなく、まずは自分自身と隣の人を起点に社会を考えていくからこそ、自分ごととして社会を探究できるのです。

参加した皆さんからの感想より。
「“シェアハピ”って素敵な考え方。未来のことを想像するのが楽しかった!」
「この高校に入りたいと思うくらい、心に残る授業でした」
授業では、京都芸術大学の学生が「ねぶた」の技法を用いて制作した買い物カートもご紹介。十年間で日本人が食べる810ℓの食品を、カゴの体積で表しています。

その他、美術では「いのちの色」という展示から食物の色彩に注目したり、英語では、いただきますという言葉の背景を掘り下げて英語に翻訳してみたり。
それぞれの教科の視点を軸に、万博のパビリオンが表現する食といのちのメッセージをより深く掘り下げるための文化的な背景なども織り交ぜた授業が行われました。


「普段考えない“いのち”について、じっくり向き合う機会になりました」
「感情や考えを“色”で表現するのがとても面白かったです」

「“いただきます”の意味が国によって違うことに驚いた」
「英語でも命に感謝を伝える方法があると知って感動しました」
「暮らし」と「学び」ひとつになる、じぶんみらい科ならではの授業
朝昼晩と食べたり、飲んだり。私たちが生きていく——いのちを持続させるためには、食べることが欠かせません。そうした、もはや当たり前の「食」も、見つめる視点を少し意識するだけでたくさんの学びがあるんです。
先生たちが視点をセットし、生徒が日々の考えや気づきを活かして主体的に学ぶ。その中で、身近なところから学びを深く掘り進める力が身につきます。
今回万博を舞台にした授業では、先生たちが万博会場に足を運び、展示を観て感じたことが散りばめられた授業が展開されていました。


.jpg?width=1800&height=1200&name=DSC09169%20(2025-07-15T15_32_20.875).jpg)

そうした現在進行形で形づくられる授業を通して、「暮らし」と「学び」がひとつになる。今回のオンライン体験授業から、そんなじぶんみらい科ならではの学校の在り方を体感していただけたのではないでしょうか。
オンライン学校説明会・体験授業は、毎月定期開催中。
ぜひお気軽にお申し込みください☺️
こちらの記事もおすすめ
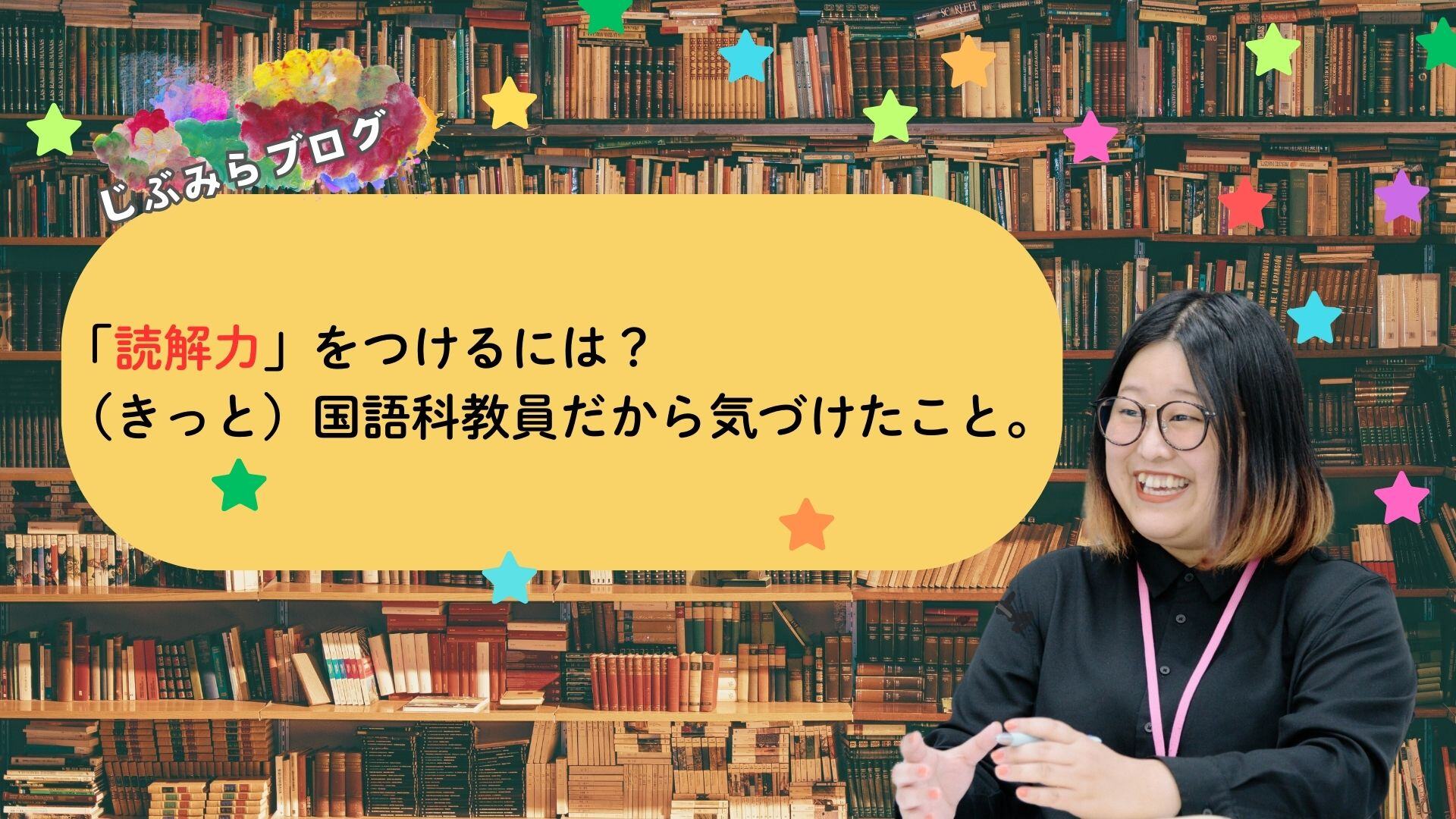
「読解力」をつけるには?(きっと)国語科教員だから気づけたこと
こんにちは。国語科の佐々野(ささの)です。
みなさん、最近「本」って読んでいますか?
10代のころの私は、スキマ時間はずっと文庫本を手にしているくらい本が大好きだったんです。電車で移動中に読んだり、座ったり寝転がったりしながら本を読み、あっという間に時が過ぎ「ああ、そろそろ晩ごはんの時間だな。」とか思う時間が好きでした。
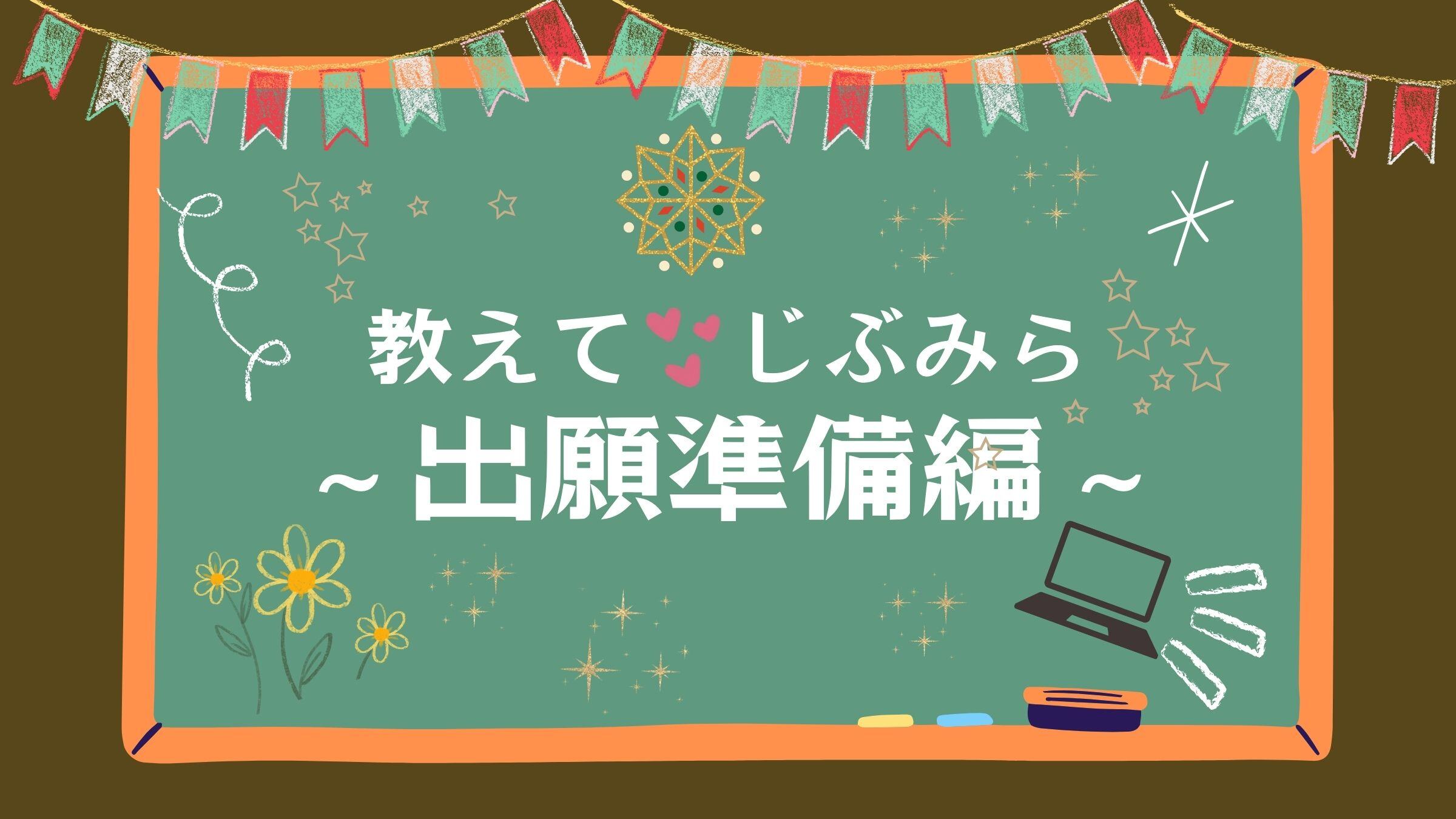
高校入試の疑問を解決!ー Web出願の手順を解説します
こんにちは🌞
じぶんみらい科で学んでみたいな…と思っていただいているあなたに向けて🎊具体的な出願についてお伝えいたします!
出願資格や詳細な出願期間等は「生徒募集要項(PDF)」に記載がありますので一度ご確認くださいね👀

通信制高校って学費はどれくらいかかるの?ーじぶんみらい科で学ぶために必要なお金について
じぶんみらい科に入学して卒業するまでに、学費はいくらくらいかかるのかな…💰
保護者の方々にも生徒さんにも気になる部分だと思いますので、本日はその点についてお答えしたいと思います!