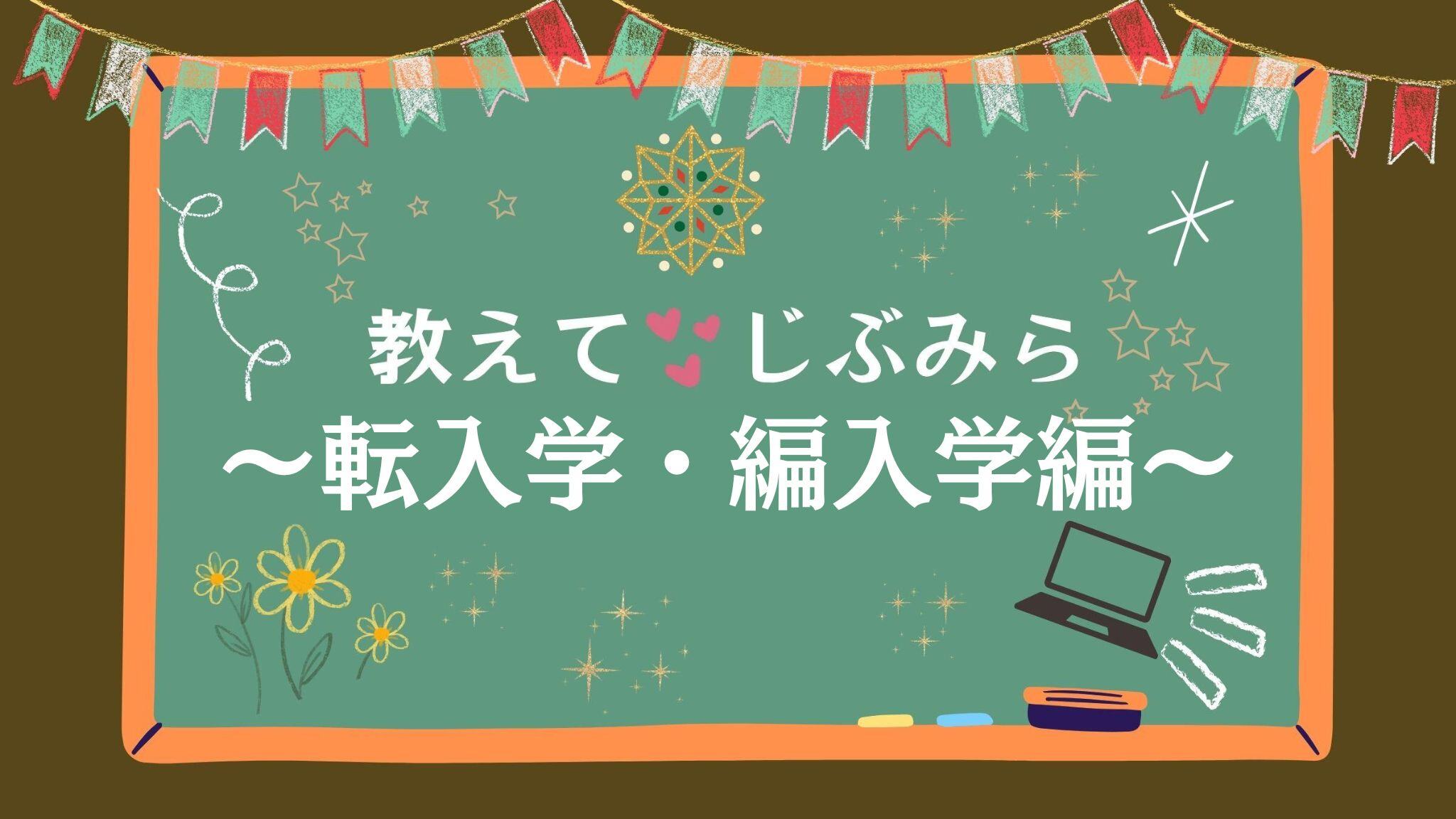「読解力」をつけるには?(きっと)国語科教員だから気づけたこと
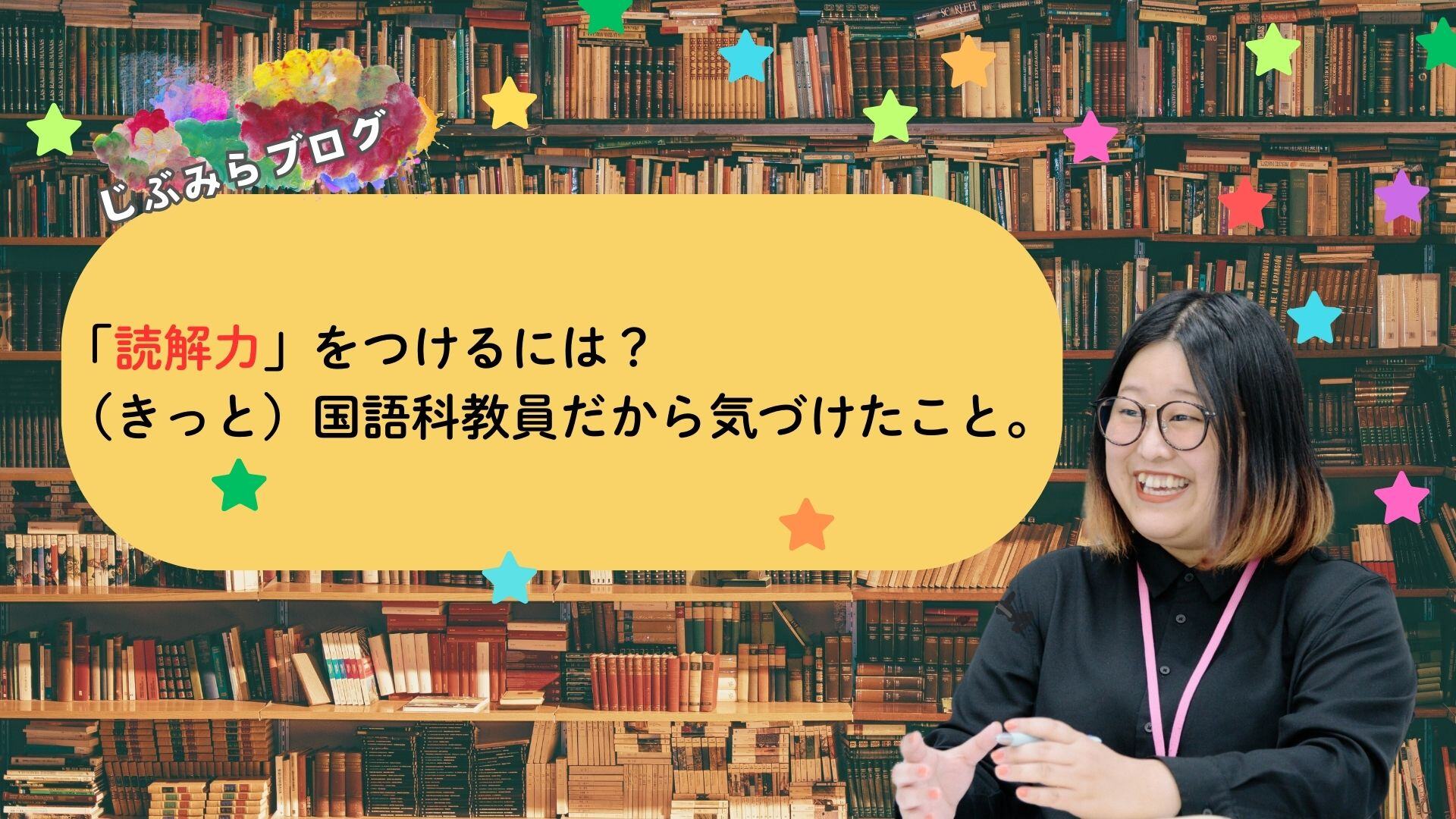
こんにちは。国語科の佐々野(ささの)です。
みなさん、最近「本」って読んでいますか?
10代のころの私は、スキマ時間はずっと文庫本を手にしているくらい本が大好きだったんです。電車で移動中に読んだり、座ったり寝転がったりしながら本を読み、あっという間に時が過ぎ「ああ、そろそろ晩ごはんの時間だな。」とか思う時間が好きでした。
心地よいスキマ時間の過ごし方が、高校から大学、社会人になってからも何度か変わるタイミングがあり、いつしか家で本を開くことが減っていきました。大人になるにつれ、文字しか載っていない「本」を開くとなると「いま読む」ための理由が必要になってしまったんです。楽しい読書がずいぶんできていないなあ。そんな風にも思い始めていました。
ただ、だからといって本を読んでいないのかというと、そうではなくて、国語の教員になったことで本を「じっくり読む」ことは増えました。どんな本を?と聞かれたら、一番多いのは教科書です。仕事で、じっくり読むことが増えたわけです。ちょっとズルい感じもしますが、じっくり教科書に掲載されている作品を読んでいるのは事実なのです。
ある意味、仕事とはいえ不思議な作業です。「じっくり読む」というのはもしかしたら、退屈で単純にも聞こえるかもしれません。ただこの作業が、退屈でも単純でもないというのは、私の中に強い実感としてあります。
「じっくり読む」からこそ見えてくるもの
確かに、大人になってから本を「じっくり読む」理由は、教員として授業をするためが主な理由。授業のずいぶん前から何度も読んで、どんな授業にしようかと考えて、うーん納得いかない。また読み込む、その繰り返しです。A組では、深く話し合えたけど、B組では少し深まり切らなかったな。何が原因か考えながら、C組だとどうだろうなと迷いながらまた読み込む。それも繰り返し何度も。こうやって、じっくり繰り返し読む時間をつくったからこそ見えてきたことがあったのです。

繰り返し読んでくたびれた本たち。
大げさに聞こえるかもしれませんが、特に小説や詩は、読むたびに大きく印象が変わることがありました。同じ作品なのに、力強く感じるときと、儚く悲しげに感じるときの両方があるのです。初めは不思議だなあくらいのことでしたが、ある時、「感じる」のは「心が動いている」ということ。「心が動いている」というのは「じっくり読まないとたどり着けない」ことだと気づいたのです。じっくり読むことで心が動いたとも言えるかもしれません。
生徒との学び合いが生み出す、特別な「読解」
生徒たちから学んだことも多く、「このメンバーだったから、こんなふうに読めた」ということが、授業ごとに起きていました。当たり前のことですが、生徒たち一人ひとりが、別の人間であるのと同時に、それぞれにこれまでの経験に紐づいた考え方や感情があり、それを大切に共有しながら、さらにじっくり読んでいく。みんなが「じっくり読む」ことで、奇跡がたくさん重なって「このメンバーだからこその読解」が実現するということがわかりました。
授業のたびにそんな幸せな体験をしている私にとっては、どの作品も宝物のように感じられます。ある意味、思い出すらも含んでいるので、作品の価値を超えているかもしれません。ふふふ
「じっくり読む」を、もっと楽しく!
そして国語科教員だから気づけたことには続きがあって、それは「読解にはじっくり読むことが絶対に必要」なのに、「じっくり読む」ことを教わる機会、体験する機会が用意されていない(もしくはとても少ない)こと。素敵な作品と素敵な生徒はもう揃っているのに、これじゃあもったいない。
だから、じぶんみらい科の国語の授業の中では、たくさんそんな機会を作りたいなと思っています。

オンライン体験授業の様子。
まずは「じっくり読む」ことを楽しむことから。心が動き出して初めて、読解が始まります。その後が気になるところだと思いますが、みんなで実際にやってみるほうが絶対に楽しいので、この続きはじぶんみらい科での国語の授業を楽しみにしていてくださいね♪ ではでは、また会いましょう~!
こちらの記事もおすすめ
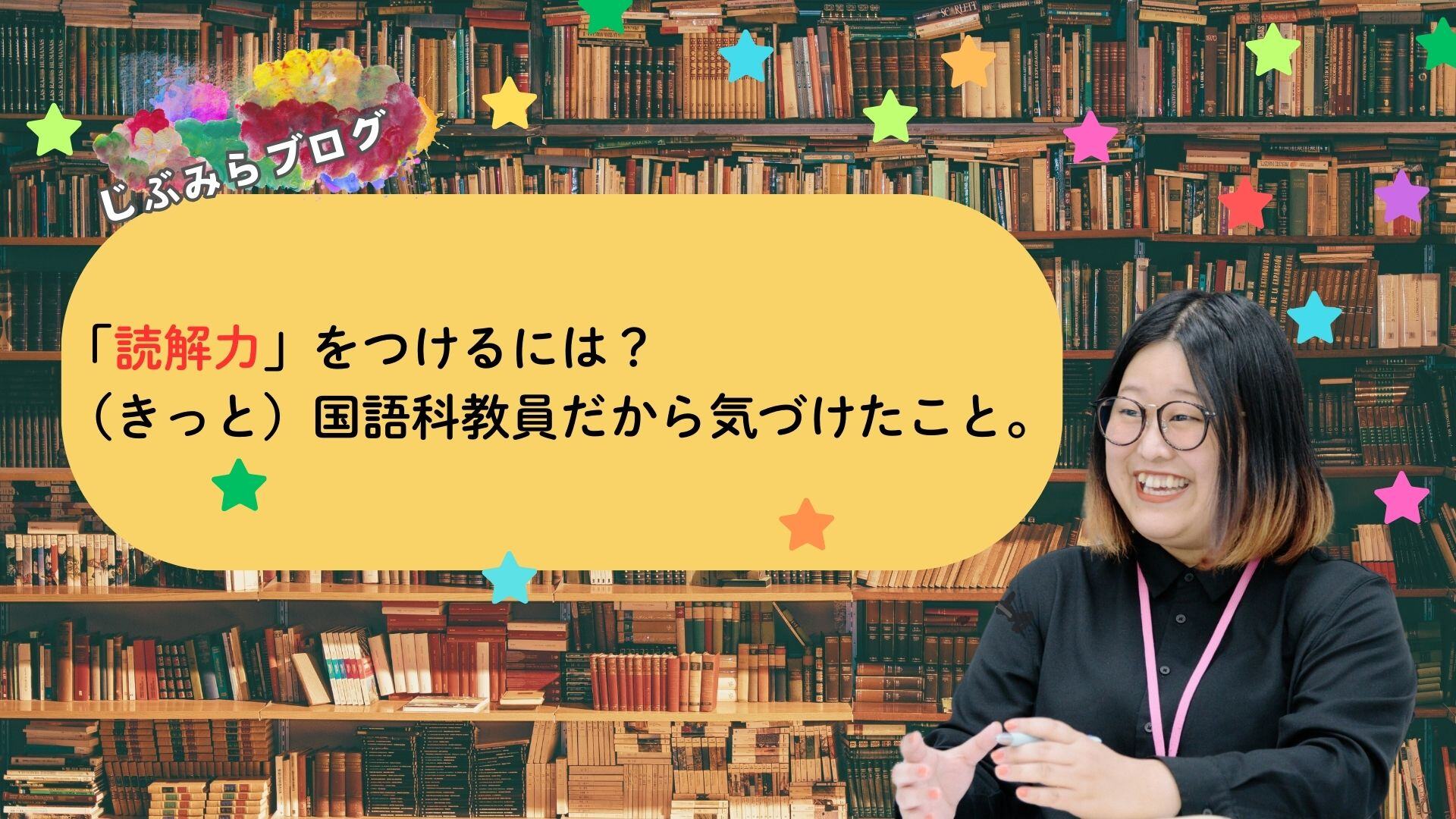
「読解力」をつけるには?(きっと)国語科教員だから気づけたこと
こんにちは。国語科の佐々野(ささの)です。
みなさん、最近「本」って読んでいますか?
10代のころの私は、スキマ時間はずっと文庫本を手にしているくらい本が大好きだったんです。電車で移動中に読んだり、座ったり寝転がったりしながら本を読み、あっという間に時が過ぎ「ああ、そろそろ晩ごはんの時間だな。」とか思う時間が好きでした。
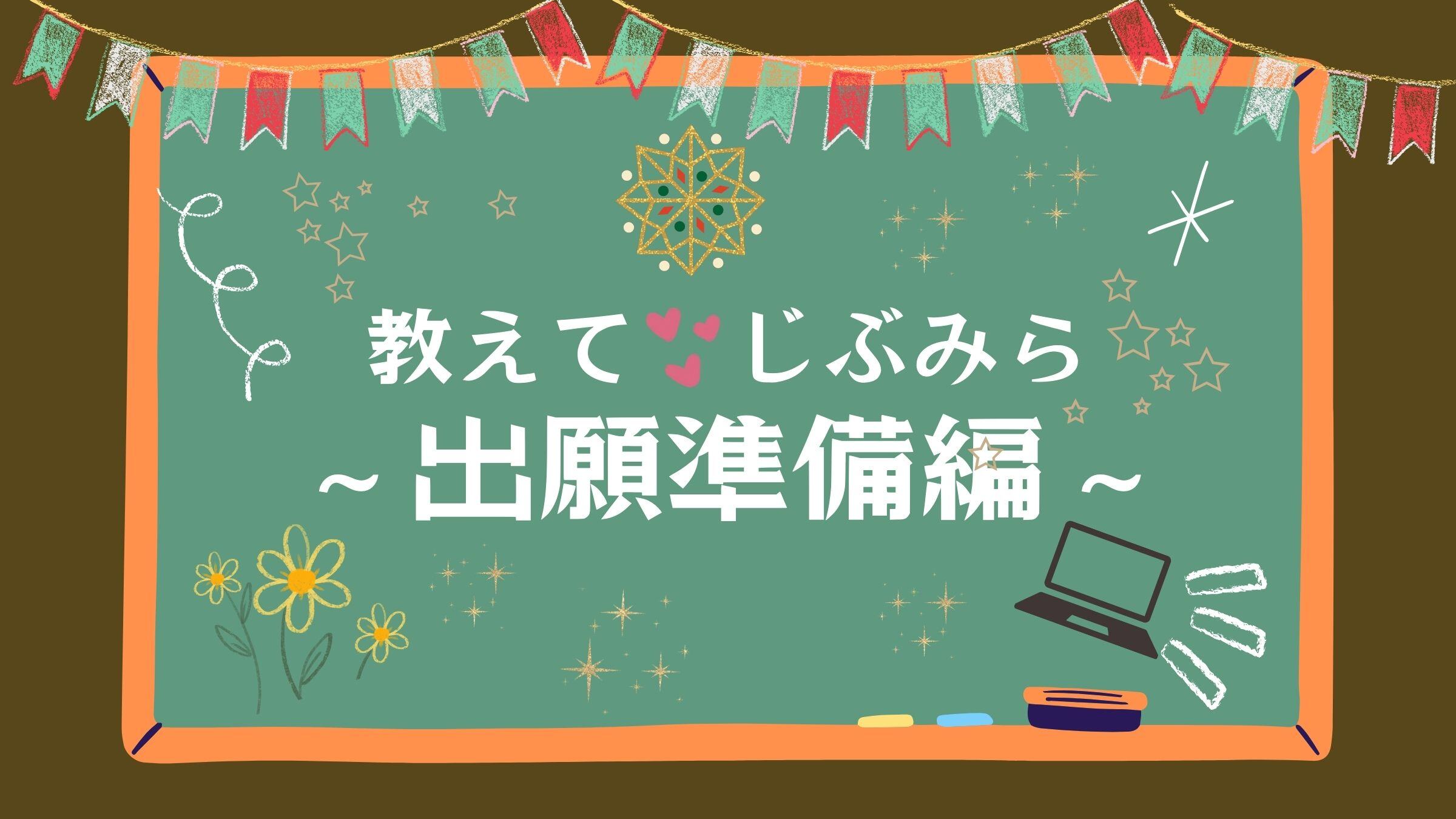
高校入試の疑問を解決!ー Web出願の手順を解説します
こんにちは🌞
じぶんみらい科で学んでみたいな…と思っていただいているあなたに向けて🎊具体的な出願についてお伝えいたします!
出願資格や詳細な出願期間等は「生徒募集要項(PDF)」に記載がありますので一度ご確認くださいね👀

通信制高校って学費はどれくらいかかるの?ーじぶんみらい科で学ぶために必要なお金について
じぶんみらい科に入学して卒業するまでに、学費はいくらくらいかかるのかな…💰
保護者の方々にも生徒さんにも気になる部分だと思いますので、本日はその点についてお答えしたいと思います!