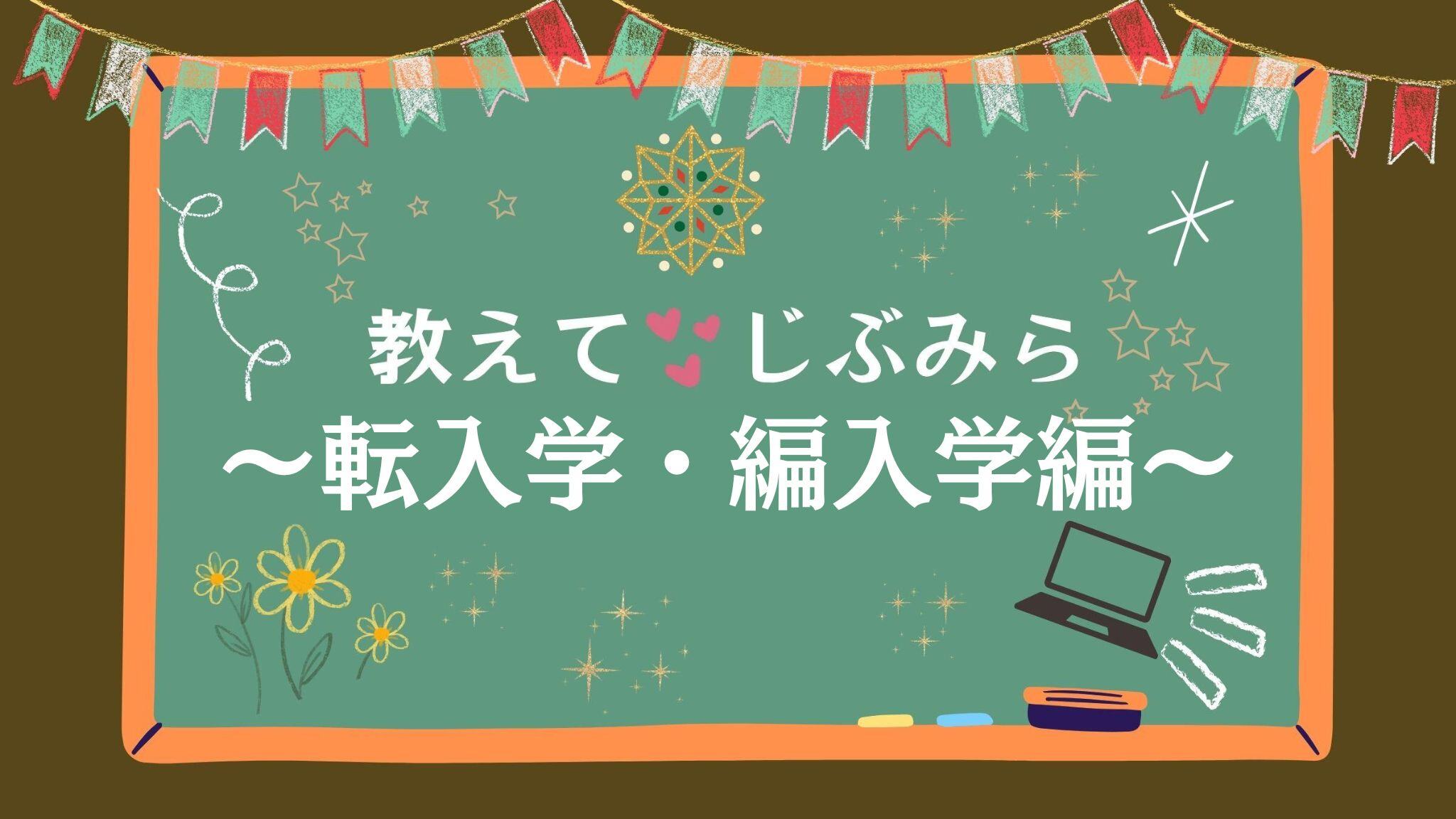学びの場所は、教室だけじゃない。― 富士山バイトで感じた「じぶんを育てる」時間

トップの写真は、東海道新幹線の車窓から臨む富士山。
毎年この季節になると思い出す場所があります。
7月1日に山開き(吉田ルート側)をしたばかりの日本一の山、富士山です。
標高3,776mを誇る富士山は、一気に登ると高山病になりやすいため、休憩しながら登山できるように山小屋が数多く点在しています。
私は10代の頃から体育が苦手で体力もなかったのですが、当時住んでいた大学宿舎に貼られていた「富士山山小屋バイト募集」のポスターを見て「これなら成長できそう!」と感じ、大学1年生の夏を富士山で過ごすことに決めました。
山小屋の生活ってどんなの?

登山道から山小屋を見上げたところ
お世話になった山小屋は、八合目(標高3,200メートルほど)にあります。30人以上の従業員が大家族のように、ひとつ屋根の下で山開きから山じまいまでの1か月~3ヶ月の間、一緒に暮らしています。
お客さんが最優先なので、バイトが寝るのも食事もすべて大部屋で、ひとりになれる空間はありません。テレビやゲームなどの娯楽は少なく、夜は体調管理のために早く寝ることが推奨されます。
それでも、毎日見ても飽きることのない朝焼けや、夜になると登山者たちのランプがまるで灯りの行列のように続いていく光景など、眼下にはいつも美しい景色が広がっていました。
時には「影富士」のように、その瞬間にしか見られない自然現象も。そんな富士山の豊かな自然と山小屋の人々に惚れ込み、毎年3ヶ月ずつ、4年間通い続ける先輩もいるほどです。


8合目付近から見える朝焼け
初バイトの厳しさを痛感
しかし、自分ひとりでカレーを作ることもままならないのに、無謀にも初バイトを山小屋に選んだために、多くの人に迷惑をかけることになります。
まず野菜がまともに切れませんでした。ピーラーがないとじゃがいもも剥けない。100合が一気に炊ける大釜を炊くと焦がす。火傷をする。掃除も先輩と比べると仕上がりがイマイチで、ならば接客はというと声が小さい。
その上、すぐに風邪を引いてしまいました。山の上では風邪が治らないそうで、地上に戻って親父さん(山小屋の主人のことをそう呼んでいました)の家で寝込みながら「こんなに役に立てないなら、もう辞めます」と伝えました。「辞めた方が楽だな、楽になりたいな」――そんな気持ちも、心のどこかにあったと思います。
しかし親父さんは何百人もの大学生を見て、自分の子のように育ててきた人。私のこともあきらめずに富士講(江戸時代を中心に富士山を神聖な山として崇めた、民間の信仰団体)の歌を教えてくれました。
不二の山登りてみれば何もなし よきもあしきもわが心なり
富士山に何かがある、と思って登ったけれど目に見える何かは何もない。
すべては自分の心次第、そう教えてくれたんですね。

ぴったりと山に寄り添うように建つ山小屋
自分を育てる場所は一か所じゃない
すべて自分の心次第、場所も周囲の評価も関係ない。本人が成長すればそれでいい。
そう伝えてくれた親父さんのおかげで、どこにいても学べるのかもしれない、とも思うようになりました。
もし、今の自分が高校生だったら、ひとつの箱の中にとどまる学校は選ばないかもしれません。自分が旅をしながら、必要なことはパソコンやスマホを通して学ぶ。学びのある場所へ向かう。そんな時代が来たこと、生徒のみんなが、家でも、外でも、自分の冒険を始めていること。
それに、私はとてもわくわくしています。
こちらの記事もおすすめ
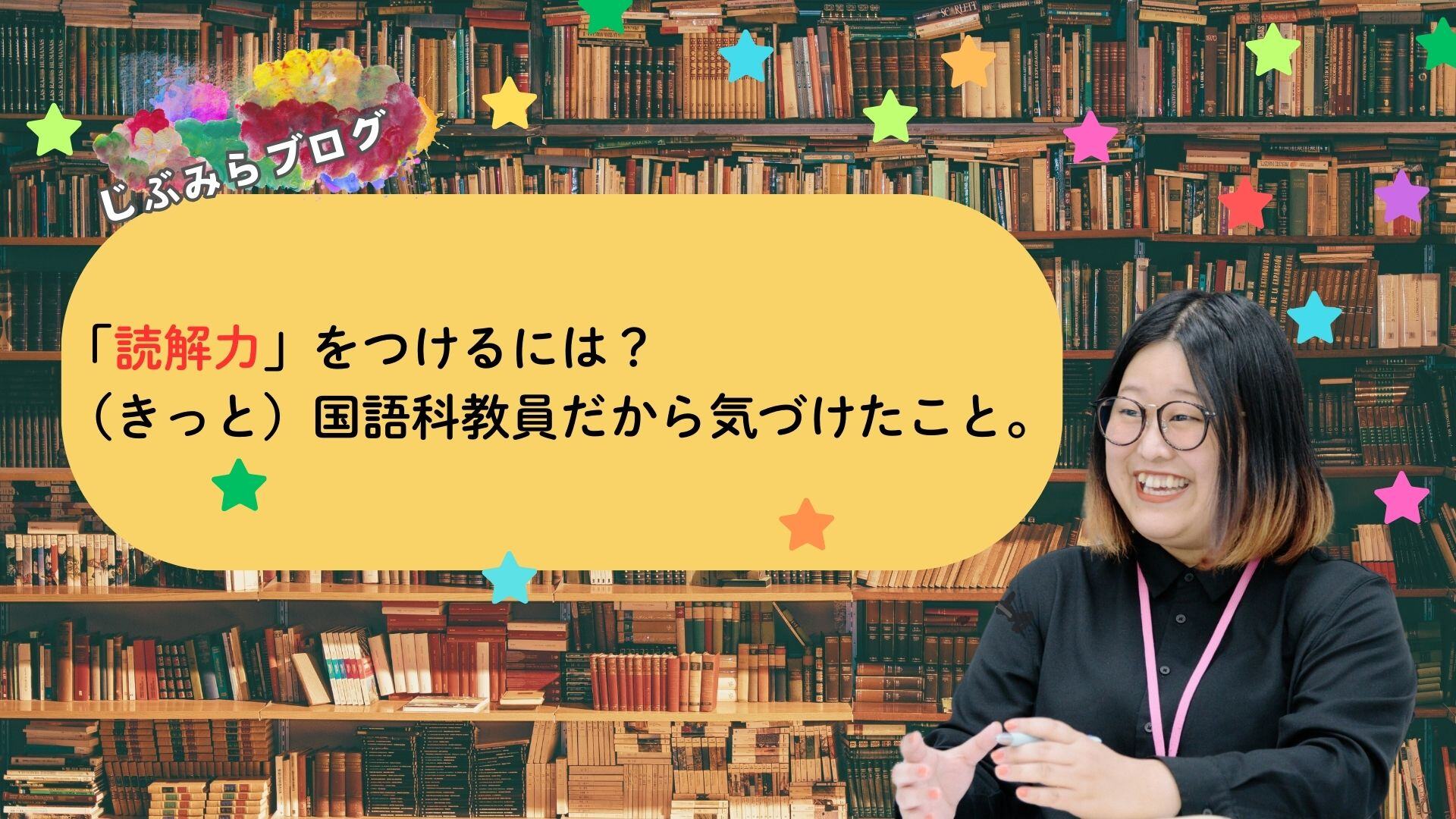
「読解力」をつけるには?(きっと)国語科教員だから気づけたこと
こんにちは。国語科の佐々野(ささの)です。
みなさん、最近「本」って読んでいますか?
10代のころの私は、スキマ時間はずっと文庫本を手にしているくらい本が大好きだったんです。電車で移動中に読んだり、座ったり寝転がったりしながら本を読み、あっという間に時が過ぎ「ああ、そろそろ晩ごはんの時間だな。」とか思う時間が好きでした。
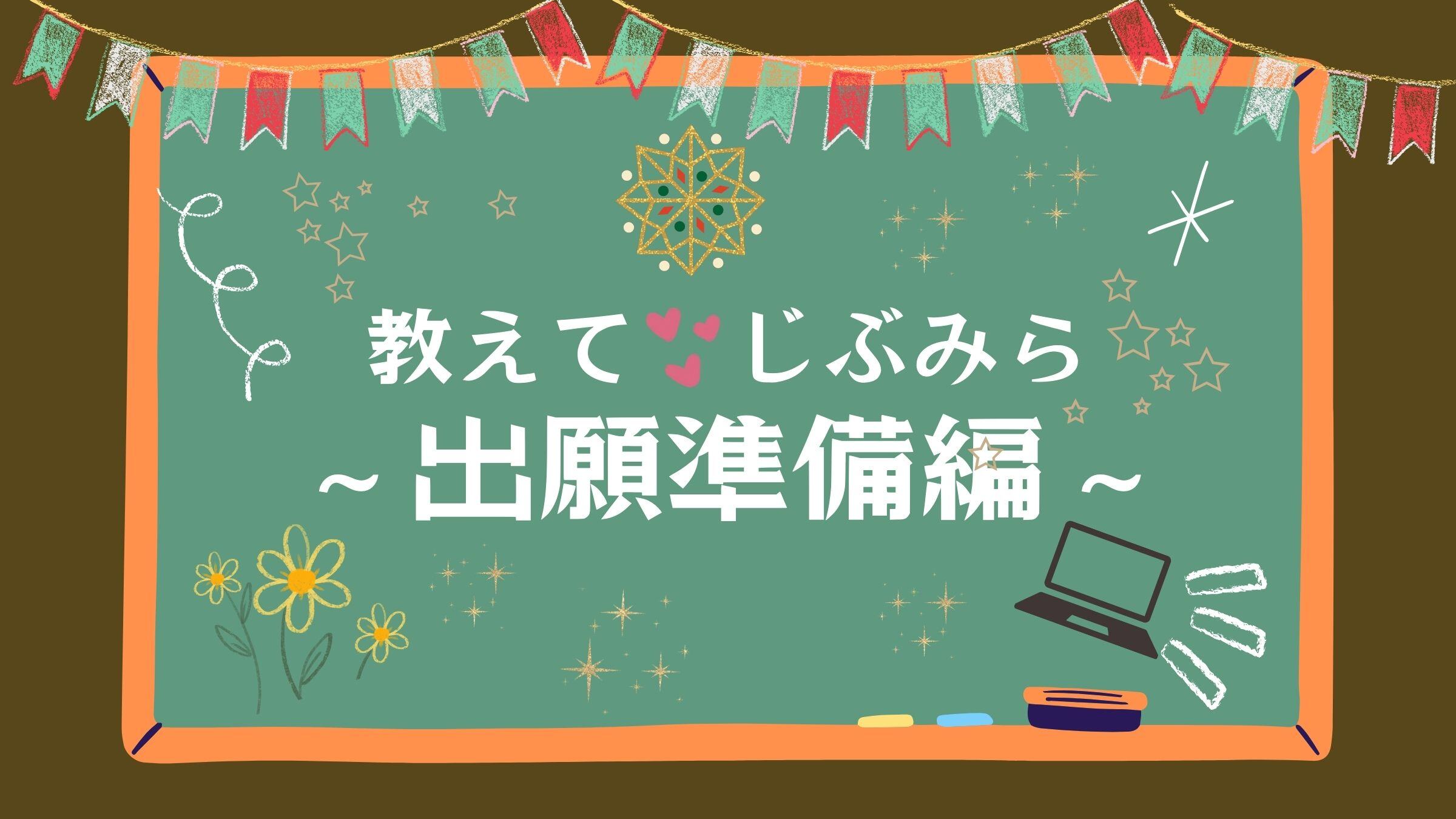
高校入試の疑問を解決!ー Web出願の手順を解説します
こんにちは🌞
じぶんみらい科で学んでみたいな…と思っていただいているあなたに向けて🎊具体的な出願についてお伝えいたします!
出願資格や詳細な出願期間等は「生徒募集要項(PDF)」に記載がありますので一度ご確認くださいね👀

通信制高校って学費はどれくらいかかるの?ーじぶんみらい科で学ぶために必要なお金について
じぶんみらい科に入学して卒業するまでに、学費はいくらくらいかかるのかな…💰
保護者の方々にも生徒さんにも気になる部分だと思いますので、本日はその点についてお答えしたいと思います!