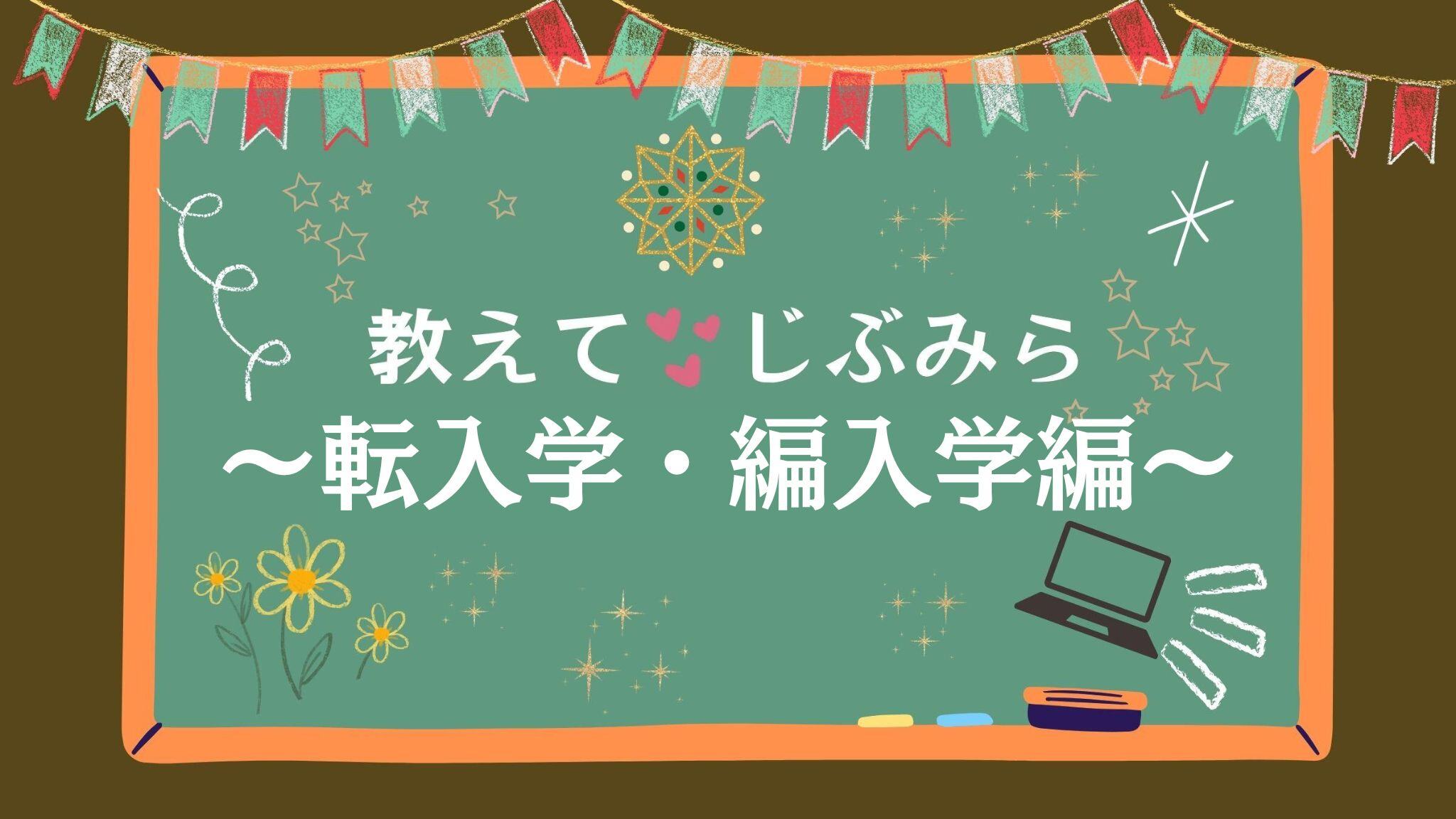英語を手段に見つける、その先の世界 − 先生インタビューvol.4 | 馬場 千恵子 先生

新学科「じぶんみらい科」で、生徒のみなさんとともに学ぶ先生たちを紹介するインタビュー!
今回は、英語科を担当する馬場 千恵子(ばば・ちえこ)先生にお話をお聞きします。
<目次>
・おわりに
英語は目的ではなく、コミュニケーションのための手段
──じぶんみらい科では、どのように英語を学んでいくのでしょうか。
まず1年生では時間をかけて、中学校までに習った内容を、be動詞から噛み砕いて説明しようと思っています。なるべく最初の段階で挫折する子、取り残される子がいないようにしたいな、という狙いです。
動画授業では、そうして文法や苦手を感じやすいものを噛み砕いて説明して、ライブ授業やスクーリングでは、習ったことをコミュニケーションの手段として使うことをメインに進めていこうと思っています。

──まずは振り返りからはじまるんですね。
そうです。2、3年生になっていくと、さらに扱う内容自体にも深みが出てきて、環境問題や戦争、差別といったことがテーマとして出てくるので、そうした社会問題のテーマそのものにも触れていけるようにする予定です。
──いろんな科目で教科を横断したコラボレーションが企画されているようですが、英語科でも?
同じ言語ということで国語とのコラボや、社会問題や歴史に関しては地理歴史や公民と一緒にやっていけたらな、と考えています。
──まさに英語は手段というか、世界に触れる入り口のひとつとして英語がある、という感じですね。
英語を知っていく楽しさももちろんあるんですけど、それを超えた先にあるものをいっぱい見て欲しくて。英語を使って何か興味のあることを深めたり、すごく身近なことで言えば観光客の方に道を教えたり。世界のいろんな情報が翻訳されるまでにはタイムラグもあるので、発信されている情報を、英語のまま自分で取り入れて考えられるようになってほしいんです。
したいことがあるから英語を学ぼうと思う。そんな動機をつかめるようなきっかけを、授業のなかでもたくさん用意できたらいいな、と。

──馬場先生にとっても英語はなにかの手段だったんでしょうか。
小学生の頃から歌手のマライア・キャリーが好きだったことが、最初に英語を好きになるきっかけだったと思います。そのうちに、海外で動物の保護活動をしたいなと思うようになって、高校では国際科に進むんですが、すごく悩んだ末に、高校で出会った先生の影響で、大学では体育の教員免許をとりました。
——一度、体育の先生に。
そうなんです。前に働いた学校で体育の先生をしていたときに、進路相談をする上で、体育の授業だけでは捉えきれない、生徒の学習面における特性を知っておきたくて、英語の免許をとってみようかなと考えはじめました。学校の後押しもあって、ブランクがあった英語の勉強をまた再開したんです。
ちょっとでも英語が話せるだけで可能性が広がったなという実感がありましたし、マライア・キャリーの振付師が来日した際に、通訳兼アテンドもすることができました。自分のできることが増えるっていう楽しさを、学びながら私自身が感じた体験でしたね。
——先生も、学びなおしを経験されてきたんですね。じぶんみらい科の英語を伝えるなかで、心掛けていきたいことはなんですか?
授業を、たくさん失敗できる場所にしたくて。やっぱり生徒はみんな頑張り屋さんだし、真面目な子も多くて、文法を考えすぎたり、声が出せない子もいると思うので、英語を話しやすい空気づくりを目指しています。発音や文法が大きな問題じゃないくらい、そのさきを目指して英語を学んでいるからねって。
人の眼鏡を通して自分を見つめる
──探究科目は先生方みなさんで考えられているそうですが、どんな授業になりそうでしょうか。
課題を解決していく前の段階の、自分の興味を見つけるっていう作業から入って、まずそこにちゃんと時間をかけていますね。「じぶんを知る」というのがテーマです。
──じぶんみらい科の先生方で、デモの授業もされてみたとか。
そうなんです。6人でやってみたんですが、たった6人でも、全員違いすぎて、意見を出すと誰の言うことも一致しないんです。心の中の「モヤモヤ」をたくさん書き出して、これは共感する、しないとそれぞれに仕分けていくと、そもそも共感という言葉の捉え方が違ったということがわかったり。印象的だったのは、保健体育科の高木先生と私はすごく真逆で、高木先生は手の届くところにあるものごとに興味や共感をもたれていて、私は自分の手の届かない範囲にすごく興味をもっていたんですよね。

──昔から海外へ関心をもたれてきたことともつながっていそうですね。
そうかもしれないです。そんな人との違いを興味深いおもしろいと感じることができる授業で、大人になっても、こんなに目から鱗っていう瞬間をもてるんだと、やってみて思いました。実生活ではそこまで深く聞けない、踏み込んだところまで相手を知ろうとできたり、そのなかで自分を発見したり。
──他者がいるからこそより見えるじぶんの輪郭もありそうです。
眼鏡というたとえをよくするんですが、探究科目でできることのひとつが、人の眼鏡を通してじぶんをみるということかなと思うんです。ひとつの物事の認知の仕方がそれぞれ違っているのは当たり前なんだけど、そこでそれってなんでなんだろうと問いを立てられるような考え方をしてもらいたいな、と。先生方とも、生徒の数だけ捉え方があるだろうから、それを踏まえて授業をつくっていこうと話しているんです。

おわりに
馬場先生は、体育の先生から英語の先生へと、社会人になってから通信制の大学に通い学びなおされた経験を、ごく自然なこととして語ってくださった姿が印象的でした。
勉強したい、と自分のなかに動機が生まれることの大切さをしみじみ感じます。
いつどんな時に動機が見つかるかは人それぞれですが、じぶんみらい科では探究科目や創造科目を通して興味の種をまいていきます。
動画授業をご紹介!
英語科の馬場先生が担当する動画授業の一部をご紹介します。「英語を知っていく楽しさ、それを超えた先にあるものをいっぱい見て欲しい」と語る馬場先生。ただ英語を学ぶだけでなく、英語を通じて世界を広げることの素晴らしさが伝わるはず。ぜひご覧ください。
Profile

馬場千恵子(ばば・ちえこ)先生 / 英語科
ニックネーム…ばばちゃん
よく読む小説家…伊坂幸太郎
『アヒルと鴨のコインロッカー』や『陽気なギャングが地球を回す』をよく読みましたね。どんでん返しのある物語がおもしろいです
こちらの記事もおすすめ
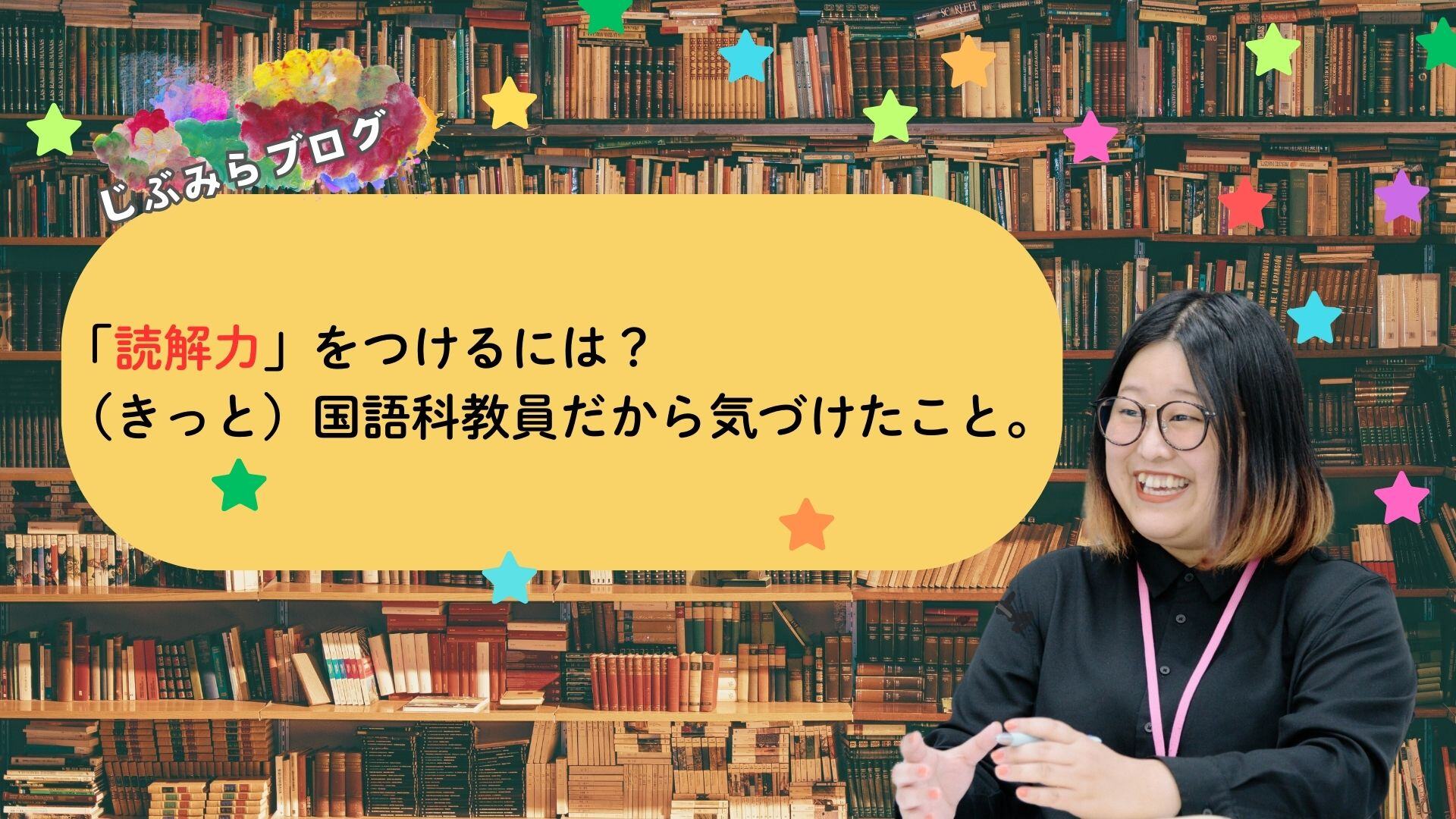
「読解力」をつけるには?(きっと)国語科教員だから気づけたこと
こんにちは。国語科の佐々野(ささの)です。
みなさん、最近「本」って読んでいますか?
10代のころの私は、スキマ時間はずっと文庫本を手にしているくらい本が大好きだったんです。電車で移動中に読んだり、座ったり寝転がったりしながら本を読み、あっという間に時が過ぎ「ああ、そろそろ晩ごはんの時間だな。」とか思う時間が好きでした。
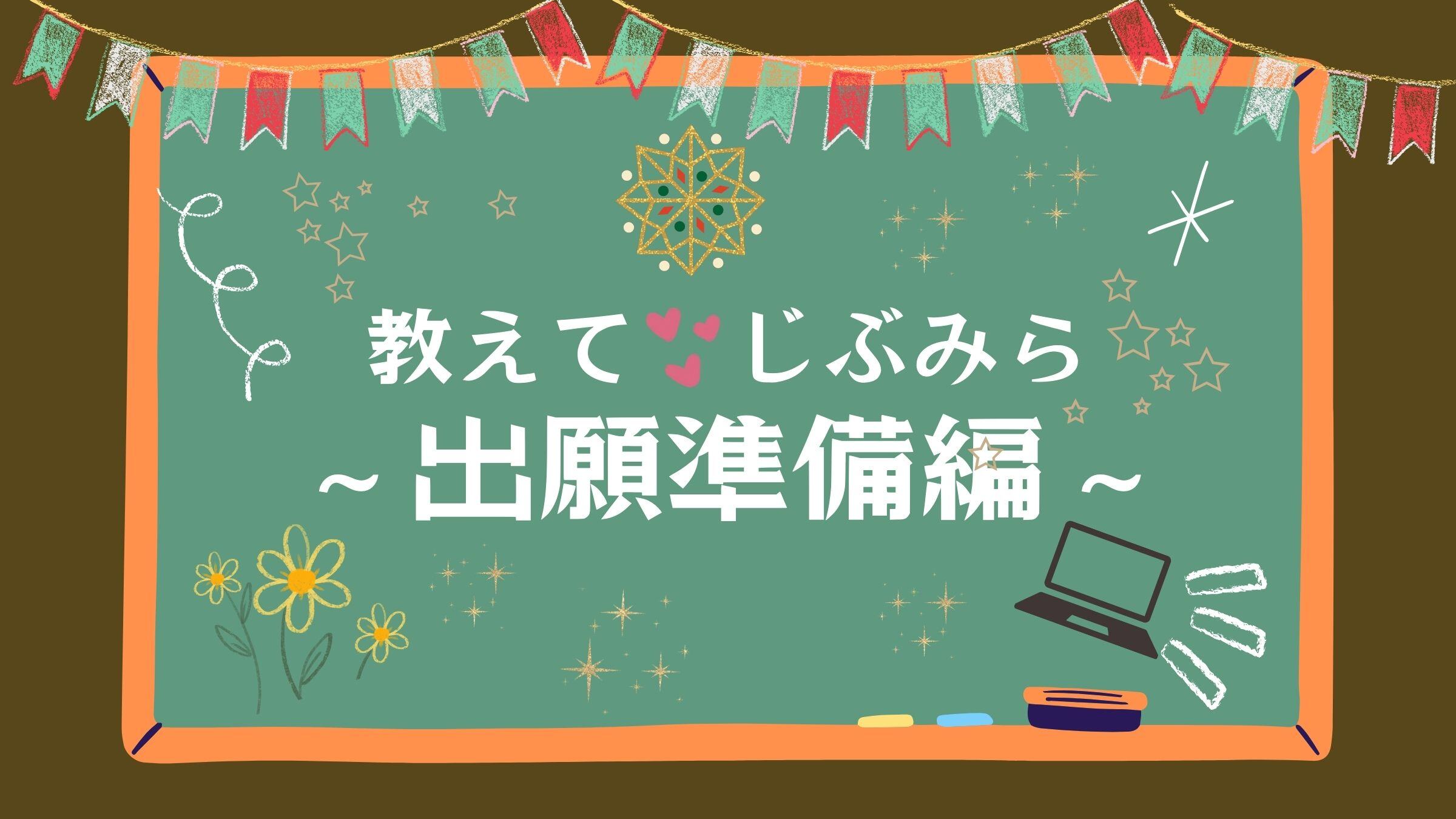
高校入試の疑問を解決!ー Web出願の手順を解説します
こんにちは🌞
じぶんみらい科で学んでみたいな…と思っていただいているあなたに向けて🎊具体的な出願についてお伝えいたします!
出願資格や詳細な出願期間等は「生徒募集要項(PDF)」に記載がありますので一度ご確認くださいね👀

通信制高校って学費はどれくらいかかるの?ーじぶんみらい科で学ぶために必要なお金について
じぶんみらい科に入学して卒業するまでに、学費はいくらくらいかかるのかな…💰
保護者の方々にも生徒さんにも気になる部分だと思いますので、本日はその点についてお答えしたいと思います!