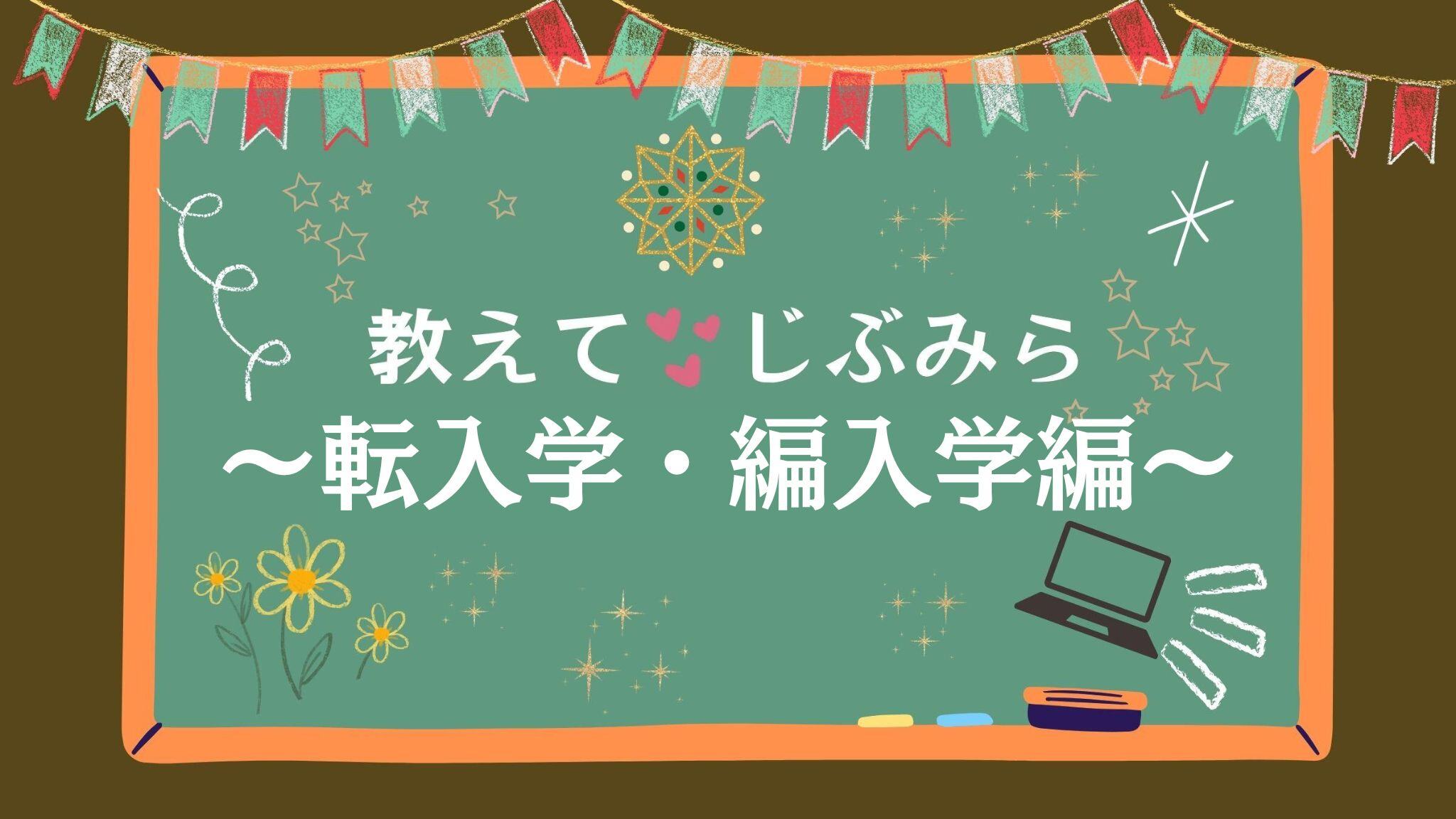経験から学びに入るおもしろさ。地歴公民は、異文化を理解し過去に学ぶ − 先生インタビューvol.5 | 久保寺 鉄平 先生

新学科「じぶんみらい科」で、生徒のみなさんとともに学ぶ先生たちを紹介するインタビュー!
今回は、地理歴史・公民を担当する久保寺 鉄平(くぼでら・てっぺい)先生にお話をお聞きします。
<目次>
・地歴公民では「異文化理解」と「ものごとを見つめる3つの視点」を大切に
・海外を巡ったあと、社会科の先生に。体験を入り口に学んでいくこと
・おわりに
地歴公民では「異文化理解」と「ものごとを見つめる3つの視点」を大切に
──じぶんみらい科の社会科では、どのような授業をされるのでしょうか?
1年生は、地理総合と歴史総合に取り組みます。まず、地理総合の目的になってくるのが「異文化理解」なんです。
──「異文化理解」ですか。
僕自身が長く海外に出ていたから感じてきたことでもあるんですが、日本の社会のなかには、今後今以上に生まれた場所や文化、風習などいろんなバックボーンをもった人たちが増えて、一緒に働いたり生活をしたりすることが、当たり前になっていく。日本人としてのアイデンティティをもつことも必要な一方で、だからと言って他者を排除しようという意識になるのは違うなと思うんです。
そんな意識がどこから出てくるかというと、相手を理解していないからなんじゃないか、というのが僕の長い旅のなかでの学びだったんです。旅先で差別を受けたこともたくさんありますが、相手を知らない、共通のものを見出せない、だから怖いという前提があって、その前提を崩すためには、まずは自分が相手のことを理解するというスタンスに立つ必要がありました。

──先生の体験から出てきた「異文化理解」だったんですね。地歴公民は暗記科目で淡々と学んでいくイメージがありましたが、じぶんみらい科では動きのある授業になりそうですね。
歴史総合では、細かな年月を暗記するというよりもあくまで流れとして掴みつつ、この出来事によって世の中がどう変わったか、それによって今の私たちの社会に実はこんな影響があった、という伝え方を心掛けています。
僕も暗記が苦手なので、内容を理解して紐づけていかないと覚えられず、勉強するのには人の4倍くらいの時間が必要だったんです。でも暗記から入らないおかげで、社会科がすごくおもしろくなりました。
──過去の出来事なんてどんどん増えていくのに、どうしてずっと遡って歴史を学ぶんだろうって思っていましたが、実は一つひとつ現代とつながっているんですよね。
歴史総合の目的がもうひとつあって、人間はBestなものはつくれないっていうことを理解してほしいな、と。Bestはできないけど、Betterはできる。最善策っていうのは、世の中の状況によって変わっていくので、歴史の教科書に書かれた過去の失敗から、いかにより良い方へもっていくかだと思うんです。
起こったことに白黒はっきりつけられないし、世の中がどんどん変わりゆくなかで、正解のない複雑なことを、みんなで考えてやっていかなきゃいけないんだよねっていうことを、まずは知っていこうと伝えたいですね。
──出来事を客観視できると、地理総合の異文化理解にもつながるような、見えない相手を想像する力がつきそうですね。
生徒のなかに別角度からの視点を増やしていくためにも、他教科とのコラボレーションを企画しています。たとえば美術の香西先生と、産業革命において同じ時代の芸術運動である印象派はどんな意味をもっていたのかという動画をつくってみようと話していたり。今はコラボ動画も試しているところなんです。

海外を巡ったあと、社会科の先生に。体験を入り口に学んでいくこと
──久保寺先生は海外を長く旅されていたそうですが、どんな流れでじぶんみらい科の先生に至るんでしょうか?
話すと長くなってしまうんですが、まず高校を卒業してすぐは消防士になりました。青年海外協力隊に行きたかったんですが、先生から「実務経験や専門性がなければ無理だ」と言われてしまって。消防官は人を助ける仕事なので、青年海外協力隊に通じるものがあると思ってたのですが、自分の理想と現実の乖離や、ルール重視の社会で行き詰まりましたね。そんな中、訓練中に怪我をしてしまったんです。いい機会だと消防士は辞めて、ワーキングホリデーを使ってオーストラリアで1年間生活しました。それが自分に合っていて。やっぱり海外って楽しいなと思ったので、一度日本に帰ってバイトしてお金を貯めて、次はロンドンを目指したんです。

──消防士からの、すごい行動力。それだけ楽しかったんですね。
でも、ロンドンの街の物価の高さと毎日曇り空なことが嫌になってきまして(笑)
航空券を調べていたら、マルタ島を見つけたんです。地中海なら気候もいいだろうし、しかも英語圏。「ここだ!」とマルタに渡って、語学学校に通って。そこでバカンスを楽しみながら語学学校に通うヨーロッパの若い人たちと友達になって、その人たちを頼りながらヨーロッパ周遊もしました。

──そこで一度日本に。
はい。それからしばらくは日本で働いたんですが、もう一度海外に出たいなと。29歳のときにシルクロードを横断しました。その旅の中でいろんなものを目にして、これを誰かに伝える手段がないかなとぼんやりと考えていたら、出会った日本からのバックパッカーの人たちに「学校の先生をやってみたら」と言われたんですよね。
帰国してその人たちに家庭教師をしてもらいながら一年かけて勉強した結果大学に合格しまして、35歳のときに教員免許を取りました。
──ものすごく濃密な人生ですね。海外で経験されたことは、普段の授業でもお話しされますか?
実体験を交えて話すことはよくありますね。その方が生徒も話がスッと入ってくるのかなと。
もともと勉強が得意じゃない、好きじゃないっていう子たちはいっぱいいると思うんですが、僕のように経験から入るという手もあるんじゃないかなと思っています。経験したからこそ、それってどうなってるんだろうと疑問をもてましたし、大学で体系的に学べるおもしろさに気づけたんですよね。
──じぶんみらい科なら、旅をしながら授業を受けるっていうこともできそうですね。
僕もそうなんですが、一箇所に拘束されることが苦手な人にも、じぶんみらい科は合っているんじゃないかなと思います。自分で考えて、タイムスケジュールを作って、やるべきことを理解していれば、自分のペースでどんな場所からどんなふうにでもアクセスできて、学ぶことができる。じぶんみらい科はそういう場所になっていけるんじゃないかと思います。
おわりに
今回お話をお聞きした久保寺先生をはじめ、どの先生も、さまざまな道を経てじぶんみらい科の先生になっていることが、この学科をよりひらかれた柔軟な場所にしているように思います。
教科ごとの学びはもちろん、その先生にしか話せない言葉を通して、生徒のみなさんをサポートしていきます!
動画授業をご紹介!
地歴・公民科の久保寺先生が担当する動画授業の一部をご紹介します。自身の豊富な海外経験を活かし、異文化理解や歴史の流れを大きく捉えていくことの大切さを解説。実際の出来事や文化の背景を理解することで、より立体的な学びを得ることができます。
Profile

久保寺 鉄平(くぼでら・てっぺい)先生 / 地歴・公民科
ニックネーム…くぼにい
おすすめ本…辺見庸『もの食う人びと』(角川文庫)
バングラデシュにはセカンドフードと言われる中古の食べ物があり、お金持ちの結婚式で出た残飯が屋台に並ぶんです。そんな世界の「食」事情が詳細に書かれてある、食にフォーカスして旅をした著者によるノンフィクションです。
京都おすすめスポット…学生食堂や喫茶店
京都芸術大学に限らず、京都にはたくさんの大学があるので、学生向けにやっている食堂や喫茶店もたくさんあります。そこで大学生たちが話すことに耳を傾けてもらうと、「大学ってこういうところなのか」と、視野がひらけてくるかも。
こちらの記事もおすすめ
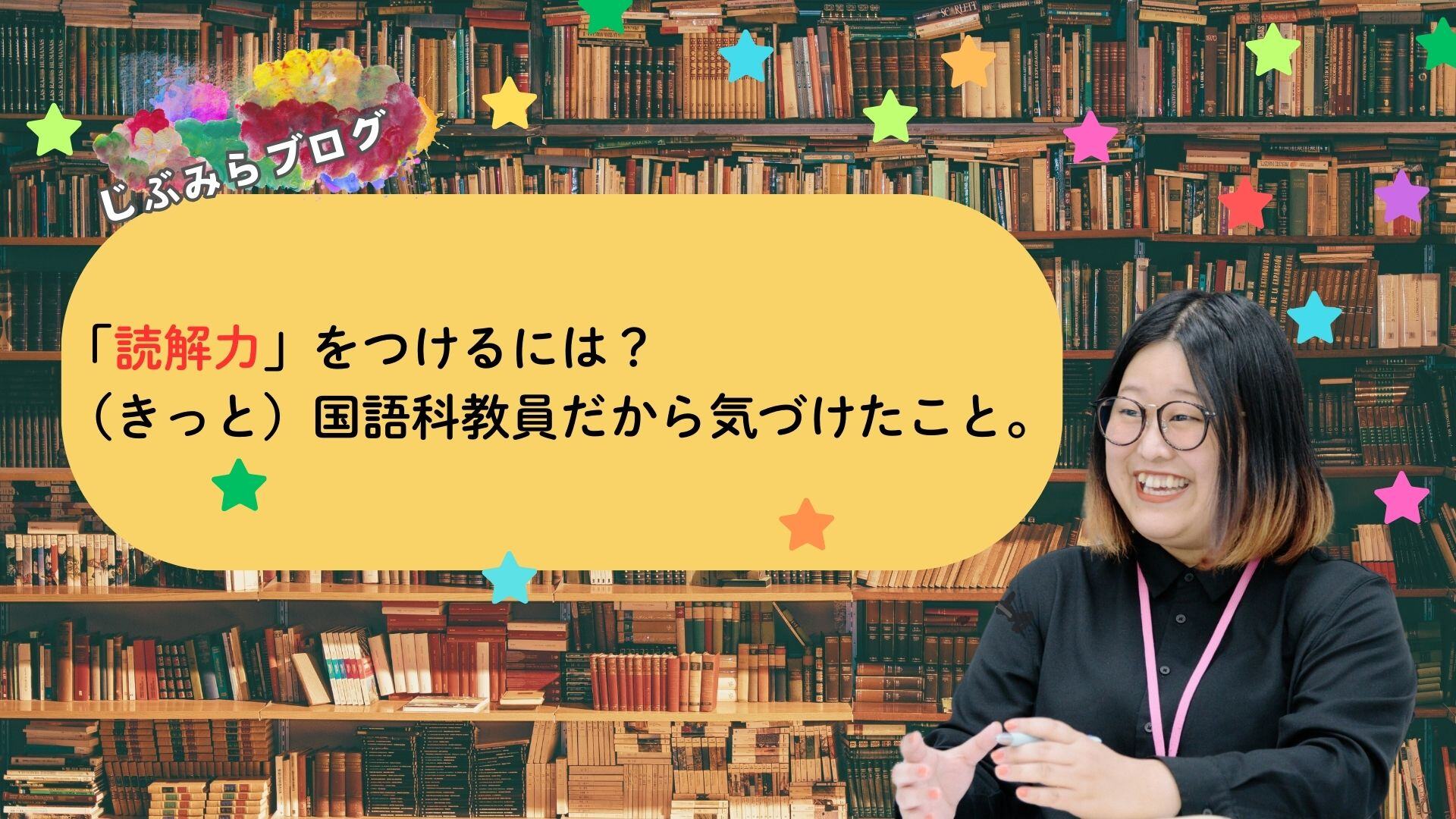
「読解力」をつけるには?(きっと)国語科教員だから気づけたこと
こんにちは。国語科の佐々野(ささの)です。
みなさん、最近「本」って読んでいますか?
10代のころの私は、スキマ時間はずっと文庫本を手にしているくらい本が大好きだったんです。電車で移動中に読んだり、座ったり寝転がったりしながら本を読み、あっという間に時が過ぎ「ああ、そろそろ晩ごはんの時間だな。」とか思う時間が好きでした。
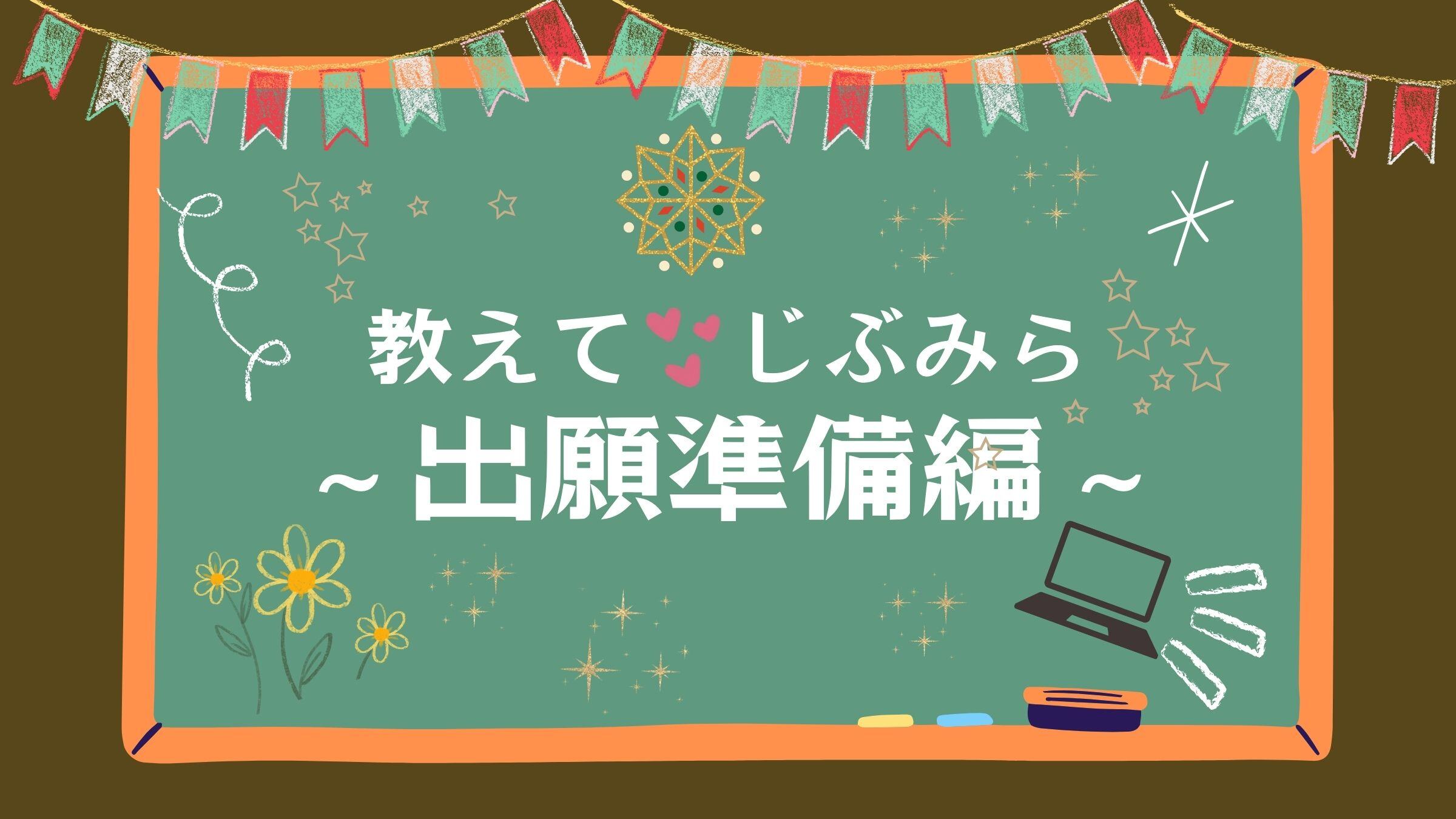
高校入試の疑問を解決!ー Web出願の手順を解説します
こんにちは🌞
じぶんみらい科で学んでみたいな…と思っていただいているあなたに向けて🎊具体的な出願についてお伝えいたします!
出願資格や詳細な出願期間等は「生徒募集要項(PDF)」に記載がありますので一度ご確認くださいね👀

通信制高校って学費はどれくらいかかるの?ーじぶんみらい科で学ぶために必要なお金について
じぶんみらい科に入学して卒業するまでに、学費はいくらくらいかかるのかな…💰
保護者の方々にも生徒さんにも気になる部分だと思いますので、本日はその点についてお答えしたいと思います!