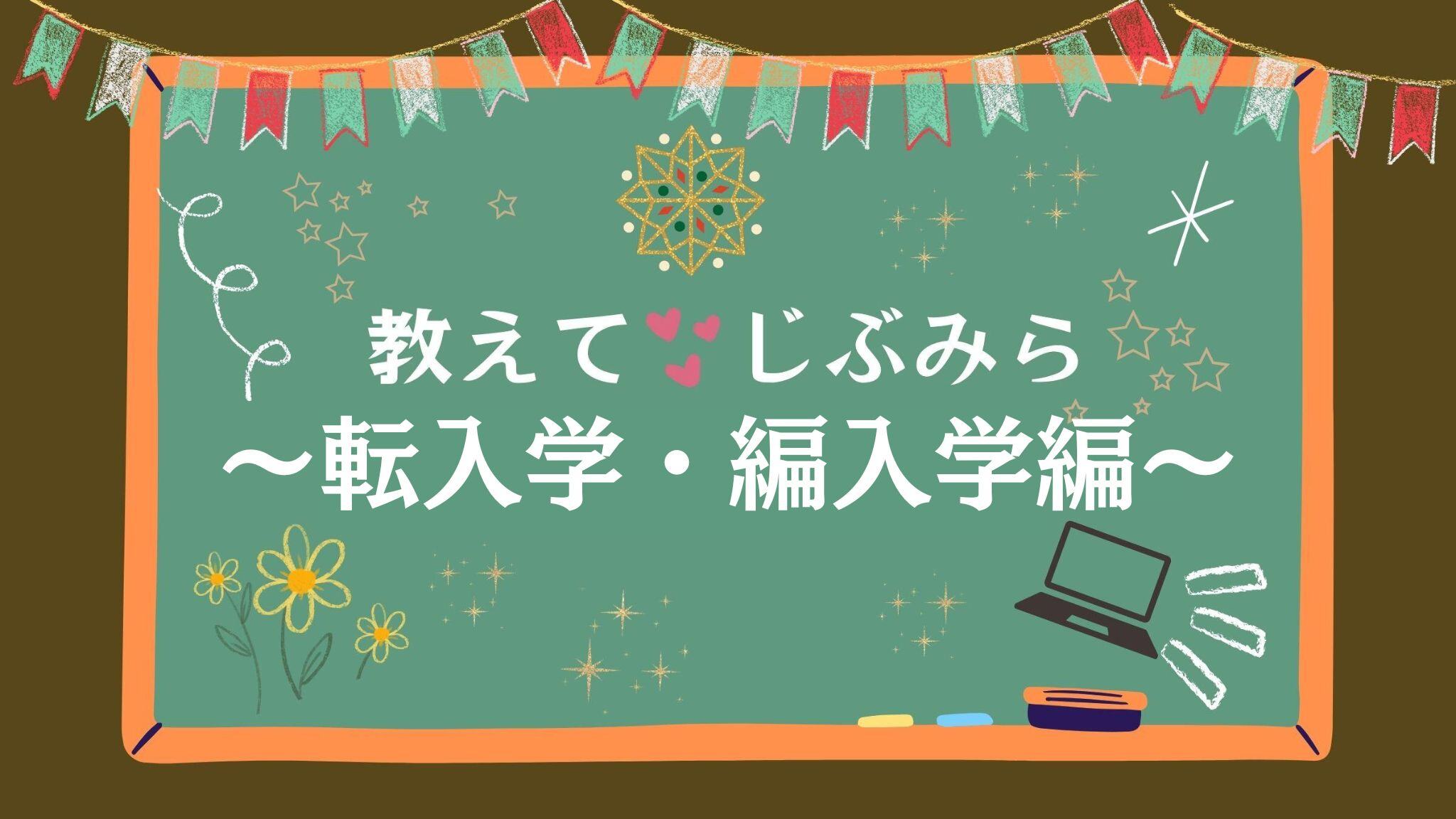生徒のもっている力を信じる。芸術を通してじぶんと向き合う美術・創造科目 − 先生インタビューvol.6 | 香西 里紗 先生

新学科「じぶんみらい科」で、生徒のみなさんとともに学ぶ先生たちを紹介するインタビュー!
今回は、美術と創造科目を担当する香西 里紗(こうざい・りさ)先生にお話をお聞きします。
<目次>
・おわりに
好きなだけ時間をかけて取り組める美術の授業
──主にオンラインで学ぶじぶんみらい科で取り組む美術は、どんな授業になっていくのでしょうか。
授業の構成は、基本に立ち返って、NHK高校講座など他の動画教材ともリンクさせながら、他教科とのつながりを大切にしていこうと思っています。淡々と手を動かすだけではなく、美術を通して生徒の興味を広げられるよう、内容に広がりがあるようにしていけたらな、と。

今は動画授業を作成中なんですが、自分がこれまで所属していた全日制の高校の授業で長く話したことがなかったと気づいて、じぶんみらい科の立ち上げをしながら、半年間勉強をしなおしました。というのも、全日制の学校だと、2時間授業のうち冒頭の10分は私が導入で話して、あとは絵を描いたり、ものを作ったりというような作業の時間なんですね。そうしてこれまで使う材料の説明ばかりしてきたので、動画では扱う素材の背景や、美術の歴史も伝えたくて。美術史も含めてしっかり基礎を身につけて、3年生になったときに、探究科目や他教科でも学んだことがいきることを目指して授業を制作中です。

──先生も日々学ばれているんですね。美術の時間では、知識を学ぶ以外にも、制作にも取り組むのでしょうか。
はい! 動画のなかで一時停止してもらったり、ライブ授業でも今作業してねと伝えたりして手を動かしてもらう予定です。授業内容はデッサンや、自分の興味のあるものを集めてつくるコラージュなど、やることはシンプルなんですが、私自身、授業の時間に応じて手を止めないといけない経験が嫌だったこともあって、じぶんの好きなだけ時間を使って、どこまでも追求してもらえるような授業をつくっています。
──ひとつの科目にどれだけ時間をかけるか上限は決まっていないからこそ、好きなだけ夢中で取り組むことができるのも、じぶんみらい科ならではの楽しみ方ですね。
そうですね。ほかにも、他教科と連携した授業をつくろうという話が進んでいます。事前に撮影・編集した動画を、生徒がいつでもみられるようにアップしておけるので、じぶんみらい科では教科横断がしやすくなったんです。
──美術の教科横断はどんな授業を?
地歴・公民科の久保寺先生とは、産業革命のときに蒸気機関車を描いたターナーや、印象派についての授業をつくろうと相談していて、基本的には1クール4本構成の動画に、5本目のおまけ動画をつくるようなイメージです。
美術の授業にも、まんがが好きな保健体育科の高木先生にまんがの授業に入ってもらったり、進路の話をするときは芸大・美大に進んだ普通科の卒業生に入ってもらったり、できるだけコラボレーションしていきたいと思っています。


──いろんな人がいろんな形で美術を楽しんでいることに触れられそうですね! 美術の時間って、ついつい人と比べて自分は下手だなと思うこともありますが、家で黙々とつくれるオンライン授業なら、作品と自分らしく向き合えそうです。
上手い下手という評価は、作品の魅力と直接関係がないことも多いです。
正直なところ、美術の成績は全員5でいいと思っているくらいです。成績表に5がついたものを好きな科目だと感じやすいから「私は美術が好きだ」と思って大人になってほしいと思っています。
──上手下手だけじゃない、自分なりの美術との関わり方が見つけられるといいですよね。そんな自由な美術の時間を通して、あえて言うなら、どんな力が身につくと思いますか?
各科目のなかでの美術の役割は、観察力を身につけること、目に見えないものを想像する力を身につけることなどにあると思うんですね。でも、美術の先生をしていると、元々生徒がもっている力の上に、小中学校へ通ううちに落ち葉が積もってしまっているような印象があって。
だから私が生徒にこんな力をつけてほしいというよりは、その子がもっているものが発揮される科目にしたいですね。
料理や数学のプロセスも、デザイン思考につながっている
──課題解決の手法であるデザイン思考が学べる「創造科目」も香西先生のご担当です。そもそもデザイン思考って、どういった考え方なのでしょうか?
実は私にとっても「デザイン思考」という、言葉のイメージだけが膨らみすぎていたんです。美術の教員だから知っておきたいし、もちろん勉強もするんだけど、思考方法を知ってもいまいち腑に落ちない。
そんななかで、「デザイン思考は実はみんなやっている」という言葉を、一緒に創造科目を担当する京都芸術大学の先生からいただいたんです。料理をつくることも、数学で式を解くために公式を選択することも、そうした一つひとつのプロセスがデザイン思考とも言えるという話をしていただいて。
──たしかに料理をするにも、「冷蔵庫のあの食材は今日までに使わないと」という課題にはじまり、食べたいものやつくる時間を踏まえて、いろんなレシピのアイデアを出し……という工程がある。それもデザイン思考と言えるんですね。
そう思って私も凝り固まっていたものがほぐれました。神棚の上にあるものをうやうやしく手渡すというよりは、そういう日常的な視点を大切にしながら伝えていく方が大事だったんだ、と思って。みんながこれまでやってきたことに、気づいてもらう。そういう仕掛けを授業のなかでつくれたらいいなと思っています。
──授業内容は、大学で行われている「マンデイプロジェクト」がもとになっているんですよね。

そうなんです。大学では毎年1年生は、マンデイプロジェクトというワークショップ形式の授業を通して「正解のない問いに、じぶんなりの答えを導き出す」ということに取り組むんですね。でもそれを高校の創造科目にそのままもってくるのではなく、高校生向けにアレンジしつつ、オンラインでもできる内容を考えています。高校生たちに、じぶんのもっている力に気づいてもらうために、身体性も伴いつつ、頭と体を使って発想してもらうような中身になっていて。大学の先生たちが授業をされてきたなかでの気づきやアイデアが入って、すごく面白い授業になりそうです。
──美術も創造科目も、「じぶんがすでにもっている力」に気づくことが、ポイントになっているんですね。
大学の先生とお話していると「こんなに生徒の力を信じてるんだ」って、それが一番衝撃で。元々もっているものを、私たち教員が邪魔せず、気づいてもらうだけでいい。しかもそれを、いろんな先生が共通認識としてもっているんですよね。
──信じてもらえることが、自信になりそうですね。
美術や創造科目の時間は、「芸術に正解はひとつじゃないから、じぶんの思っていることを大事にしていいんだよ」と伝えたいですね。
おわりに
教育現場を見るため、短期でデンマークに留学した香西先生。そこでのびのびと学ぶ子どもたちの姿を目にしたことで、日本でもこんな学校ができないだろうかと考えたことが、附属高校に来たきっかけだったと言います。
香西先生をはじめ、じぶんみらい科の先生は、「先生」の目線だけで語るのではなく、学生時代に感じたモヤモヤも喜びも鮮明に語る姿が印象的。じぶんみらい科では、そんな、いい意味でバラバラな体験と個性をもった先生が働いています!

動画授業をご紹介!
美術科の香西先生が担当する動画授業の一部をご紹介します。美術で養われる力は「観察力と目に見えないものに対する想像力」と語る香西先生。上手い下手ではない美術の魅力が伝わるはずです。ぜひご覧ください。
Profile

香西 里紗(こうざい・りさ)先生 / 美術科
ニックネーム…りさてぃ
好きな本…ミヒャエル・エンデ『モモ』(岩波書店)
小学4年生のときに、おもしろいことを言いたいだけのはずが、クラスメイトを泣かしてしまうという大失敗をして、言葉ってなんて危険なんだと思ったんです。そんなときに初めて『モモ』を読んで、人の話を聞くだけで本当のコミュニケーションをとることって可能なんだ、無理に話そうとしなくていいんだ、と教えてもらいました。
こちらの記事もおすすめ
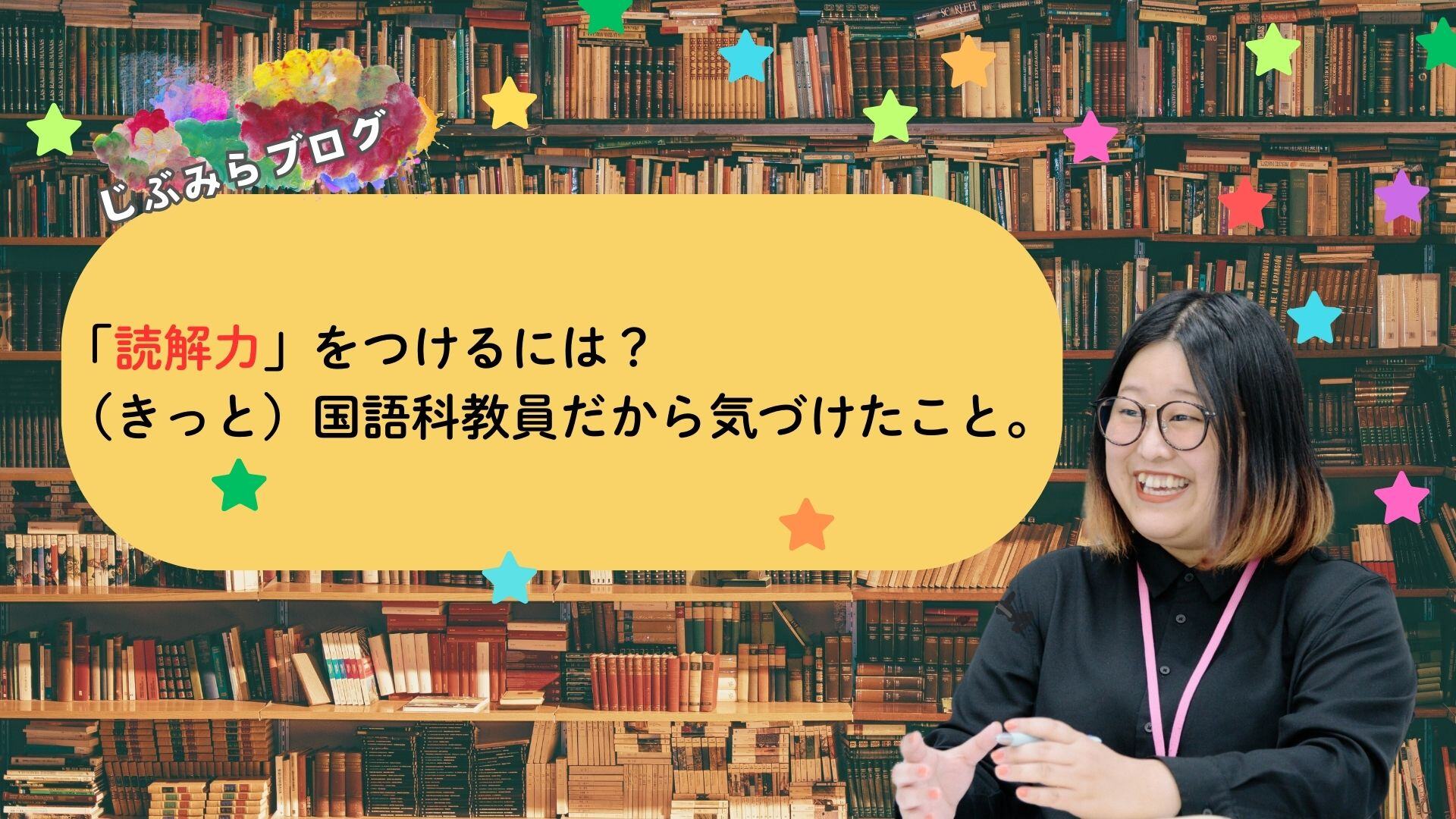
「読解力」をつけるには?(きっと)国語科教員だから気づけたこと
こんにちは。国語科の佐々野(ささの)です。
みなさん、最近「本」って読んでいますか?
10代のころの私は、スキマ時間はずっと文庫本を手にしているくらい本が大好きだったんです。電車で移動中に読んだり、座ったり寝転がったりしながら本を読み、あっという間に時が過ぎ「ああ、そろそろ晩ごはんの時間だな。」とか思う時間が好きでした。
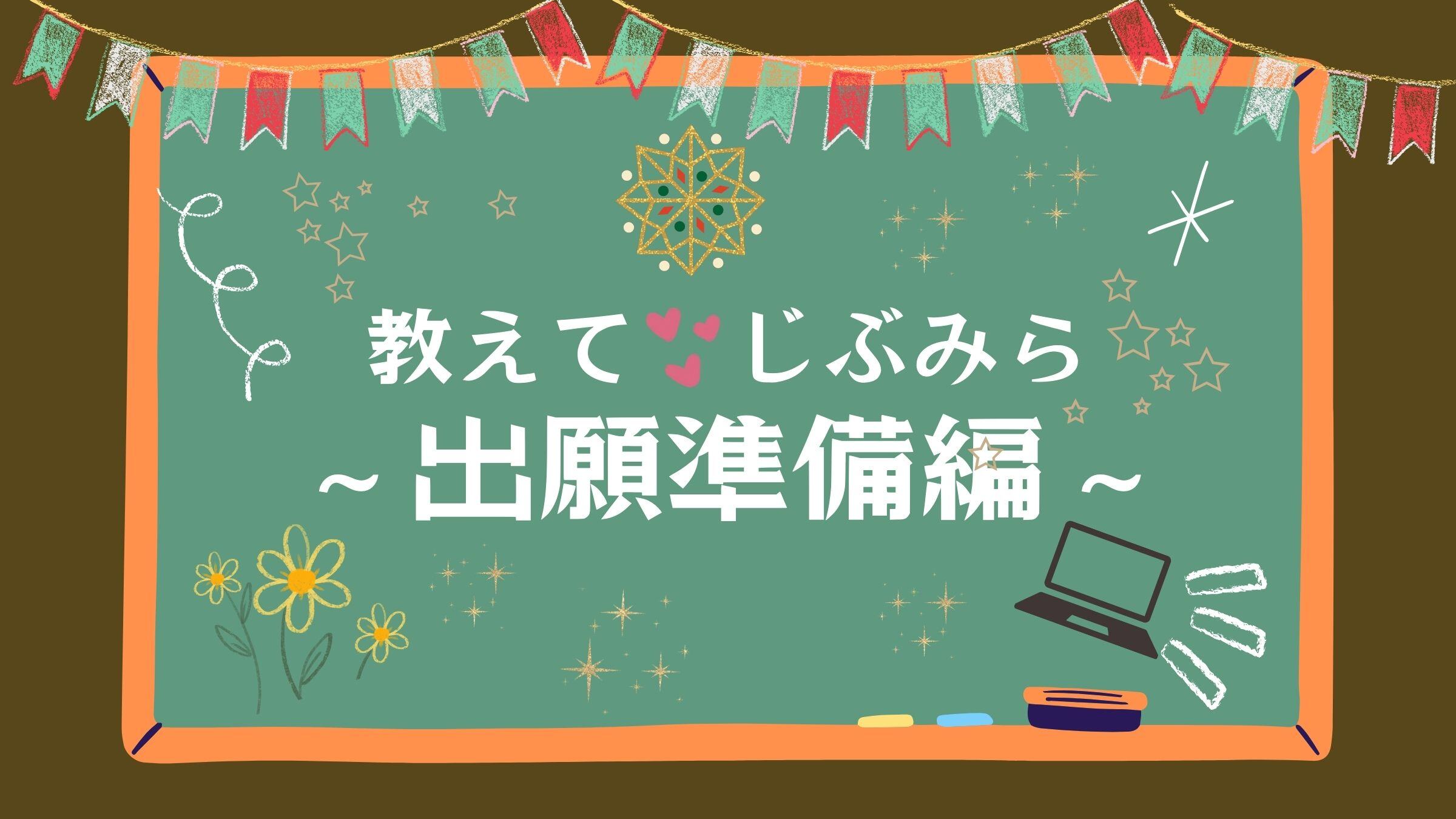
高校入試の疑問を解決!ー Web出願の手順を解説します
こんにちは🌞
じぶんみらい科で学んでみたいな…と思っていただいているあなたに向けて🎊具体的な出願についてお伝えいたします!
出願資格や詳細な出願期間等は「生徒募集要項(PDF)」に記載がありますので一度ご確認くださいね👀

通信制高校って学費はどれくらいかかるの?ーじぶんみらい科で学ぶために必要なお金について
じぶんみらい科に入学して卒業するまでに、学費はいくらくらいかかるのかな…💰
保護者の方々にも生徒さんにも気になる部分だと思いますので、本日はその点についてお答えしたいと思います!