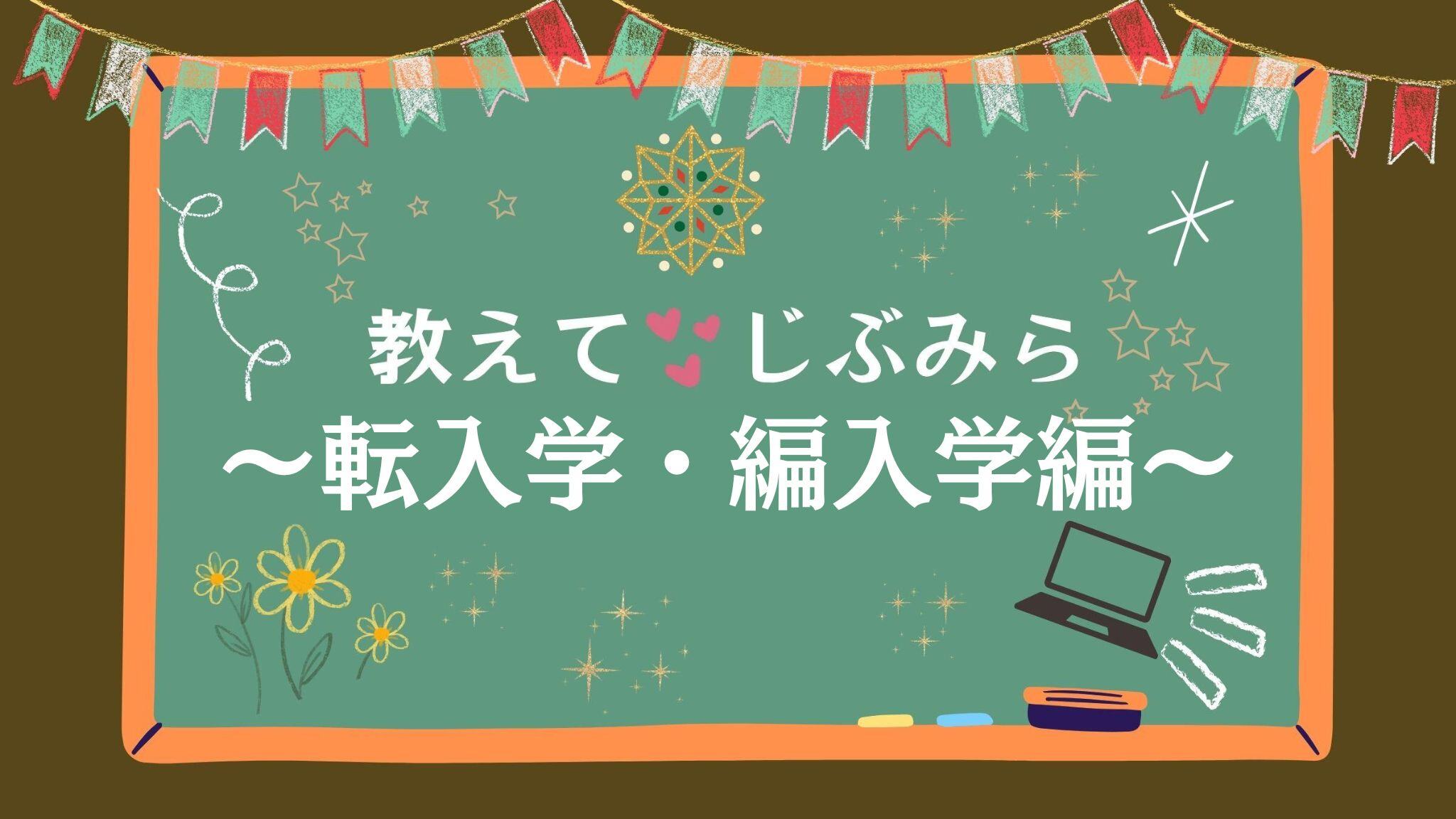なぜサビから始まるの? ヒット曲から情報社会を読み解く!

こんにちは! 数学科と情報科を担当しています「のなのな」です。今回は「情報科」としての記事をお届けしたいと思いますが、少し趣向を変えて自分の好きな「音楽」と結び付けてみました。情報の授業で音楽がどのように関係してくるのか不思議に思われるかもしれませんね。
「え、もうサビ!? 」ヒット曲に隠された「情報」って?
先日、ある音楽ストリーミングサービスが3か月無料キャンペーンだったので加入し、音楽を聞きながら作業を進める毎日です。異世界転生系のアニメをみるのも好きなのですが、その主題歌などに採用されるような最近の曲を聴いていると、いくつかの特徴があるなあと考えています。みなさんは何か感じることはありますか?
①イントロがなく、いきなり歌からスタートしている。
昔は最初にイントロがあって、だんだん盛り上がってからようやく歌い出しだったのですが、最近はイントロがなくいきなり歌からスタートしている曲が多くなった気がします。中には、サビから始まる歌もありますね。これはきっと、音楽をはじめとした豊富なコンテンツに慣れすぎてしまって、好きかそうじゃないかを「秒」で判断するようになったからではないかなと。
皆さんもShort動画などで「つまらない!」と感じたらすぐにスワイプしてしまいませんか?昔は現金を握りしめてレコード(わかるでしょうか?)やCDを購入し、家に帰ってプレーヤーの前に座って楽しみに聴いていたのです。さっとスワイプするなんて考えられず、大げさに言えばそれはレコードやCDをたたき割るようなものです。今は秒で罪悪感もなしに次の曲へと移ることができます。そのため、イントロなんて悠長にやってられない、という感じなのでしょうか。
②「エモい」コード(和音)を多用している。
私はピアノを弾けませんが、曲に使われているコードに注目して聴くことがあります。getWild進行や丸サ進行など一定のコード進行が流行っていたのですが、おしゃれでエモいコードをさりげなく使い、それがそのアーティストのテイストにもつながっています。

③今までにはありえない転調のパターンがある。
②と同様に、ありえないパターンの転調も増えてきました。転調するためのきっかけとなる小節があり、盛り上がるために音程が上がるのが定石でしたが、最近の曲はサビに何の前触れもなく調の雰囲気が変わるとともに、さらに音程が下がる転調なども採用されるようになってきました。
BGMじゃない、ちゃんと聴いてる? 「聴き流す音楽」の時代

これら私の3つの考察から言えることは、秒で心をつかみ、さらに意表を突くエモさで脳内のドーパミンがあふれ出る感覚を満たしてくれるような曲が人気を集めているということ。音楽ストリーミングサービスは画期的で便利ですが、音楽はじっくり味わって聴くというよりも、聴き流すものになってきつつあるように感じるのです。自分が気に入ったジャンルやアーティストの曲があり、自分なりの楽しみ方で聴いていると思いますが、一方で先に述べたようなエモくて誰もが心地よくなってしまう曲を「選ばされて」聴いている自分もいるような気がします。
また、AIを使って歌詞や好みのテイストを入力すれば一瞬にして曲ができてしまうサービスも広まっています。楽譜やコードの知識や技能がなくても誰もが音楽を制作し、動画とのコラボしながら世に発表することができるようになってきました。じぶみらのテーマソングも作ってみましたが、短い時間でなかなかのクオリティでした。(一方でコード理論や作曲の方法を自分なりに試してきた身としてはショックを受ける部分もあります。)

じぶみらソング
https://suno.com/s/bP8UQOYydP6rI9hK
「自分らしい時間」を取り戻そう!
さて、音楽から情報との関連を考えてみました。社会の変化に応じて音楽のあり方も変化していくように、現在は動画や音楽、ゲームなどがほぼ無料で楽しめ、豊富なコンテンツで囲まれて生活しています。それで幸せになったという見方がある一方で主体的に自分が楽しめているかというと、ストレスを緩和させるためであったり何となく見続けていていて、しだいに飽きてしまい、より強い刺激のあるものを求めがちになってしまうかもしれません。
いつの間にか時間が過ぎてしまった…という経験は私にもたくさんあります。そうしたことに気づき、自分らしく豊かに生活していくかを見直してみることが必要かもしれません。
情報科の授業で「作ろうマイルール」というトピックがあります。自分の1日のスマートフォンの利用時間を調べて、どのような問題点があるかを発見し、「スマートフォンに頼りすぎずに、自分らしい生活を送るにはどうすればよいのだろうか?」を考えるワークです。

私たちは、良い面も悪い面も含めて、情報があふれる社会に生きています。その中で、大切な情報を見つけたり、逆に不要な情報を手放したりして、「よりよく生きる」ことが求められます。
最後は、「メディアとの上手な付き合い方」に着地しました。ここまでお読みいただいたということは、このブログが「イントロでスワイプ」されなかったということです。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こちらの記事もおすすめ
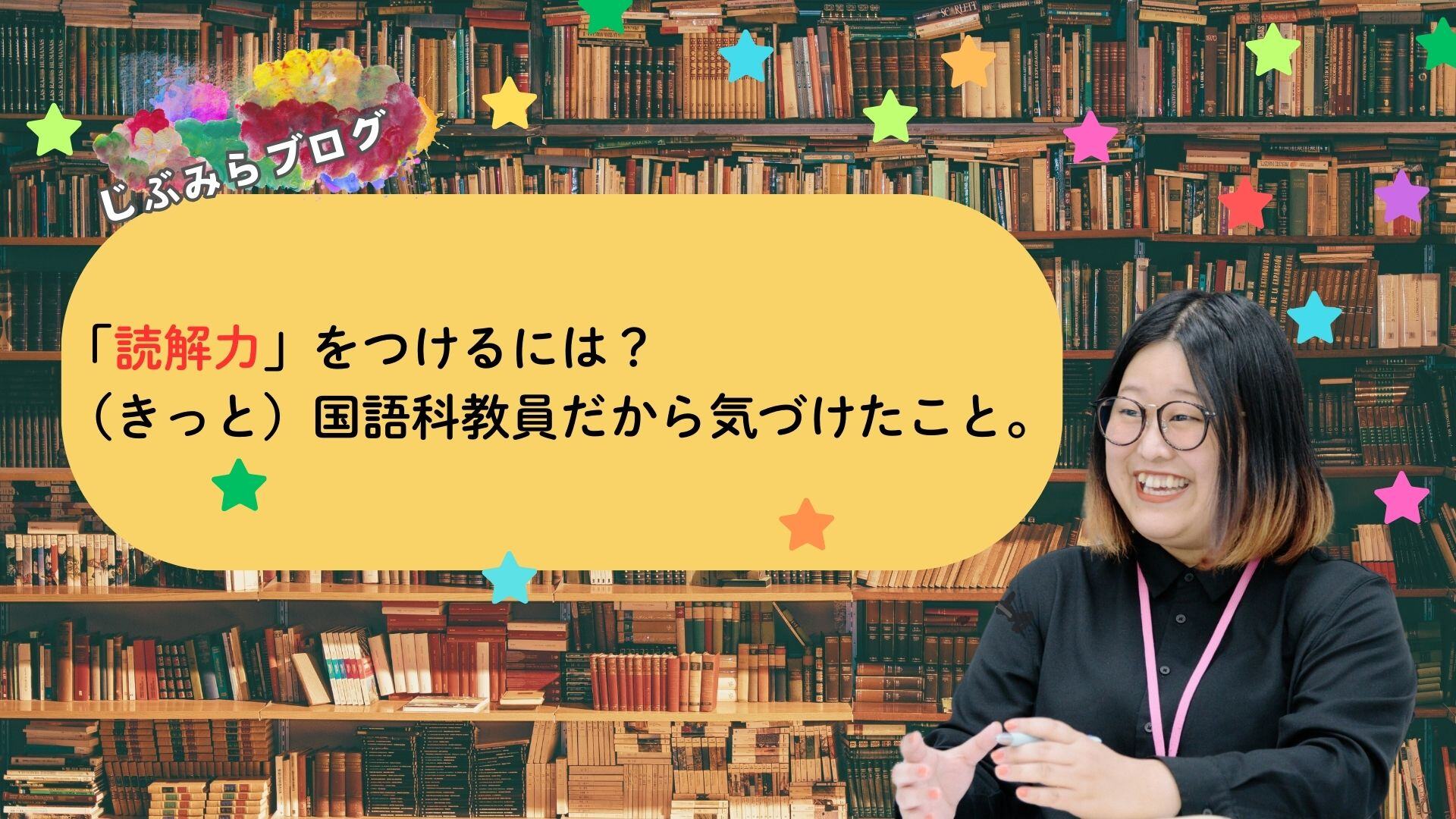
「読解力」をつけるには?(きっと)国語科教員だから気づけたこと
こんにちは。国語科の佐々野(ささの)です。
みなさん、最近「本」って読んでいますか?
10代のころの私は、スキマ時間はずっと文庫本を手にしているくらい本が大好きだったんです。電車で移動中に読んだり、座ったり寝転がったりしながら本を読み、あっという間に時が過ぎ「ああ、そろそろ晩ごはんの時間だな。」とか思う時間が好きでした。
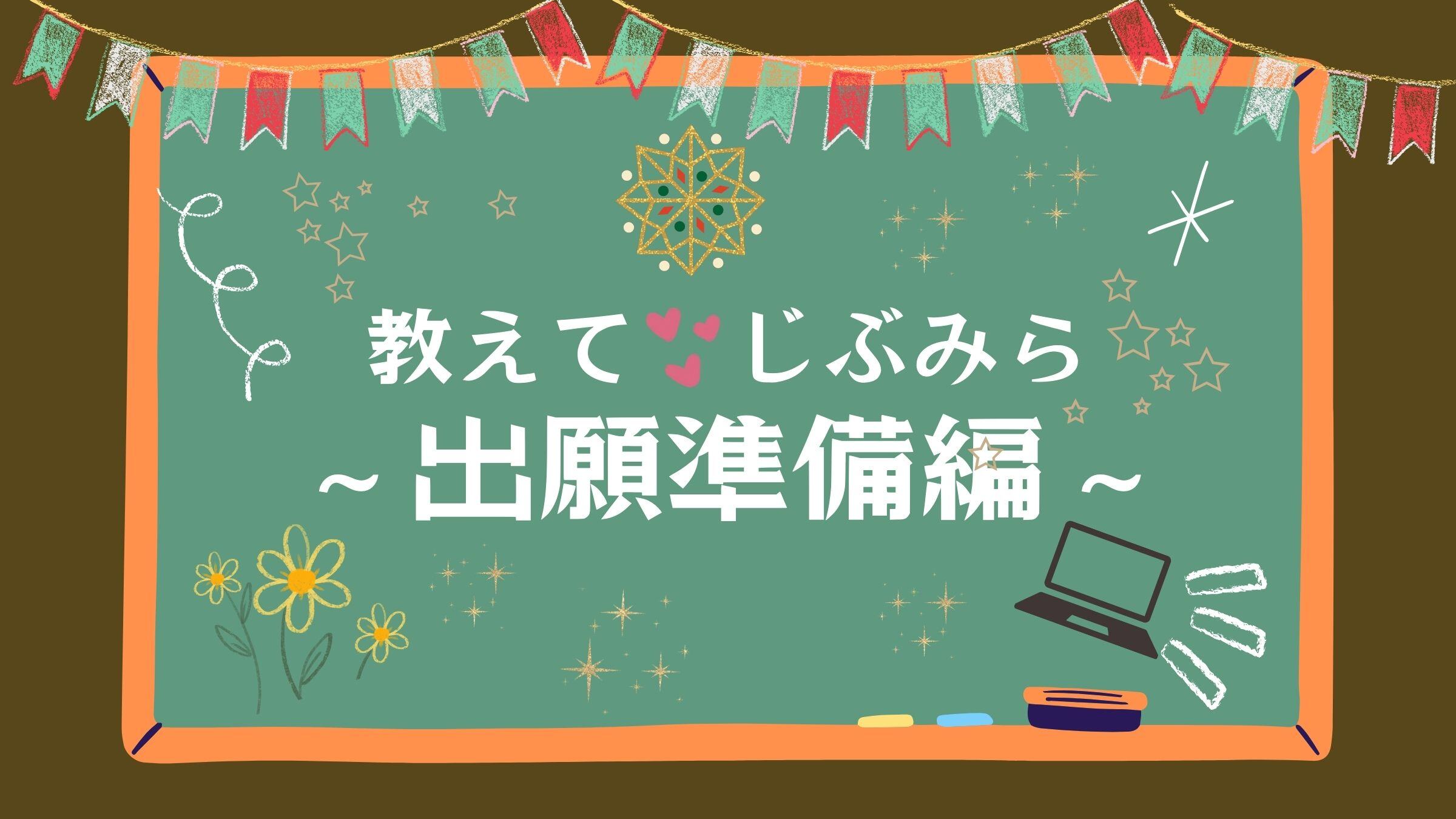
高校入試の疑問を解決!ー Web出願の手順を解説します
こんにちは🌞
じぶんみらい科で学んでみたいな…と思っていただいているあなたに向けて🎊具体的な出願についてお伝えいたします!
出願資格や詳細な出願期間等は「生徒募集要項(PDF)」に記載がありますので一度ご確認くださいね👀

通信制高校って学費はどれくらいかかるの?ーじぶんみらい科で学ぶために必要なお金について
じぶんみらい科に入学して卒業するまでに、学費はいくらくらいかかるのかな…💰
保護者の方々にも生徒さんにも気になる部分だと思いますので、本日はその点についてお答えしたいと思います!